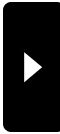2009年12月31日
ミッキープリン。
 今、親戚もうちにやってきて、十人で紅白を見ているんだけど、姫(小3女子)が作った巨大ミッキープリンが登場、お茶の間は大混乱に。
今、親戚もうちにやってきて、十人で紅白を見ているんだけど、姫(小3女子)が作った巨大ミッキープリンが登場、お茶の間は大混乱に。とにもかくにも、みなさん、よいお年を〜〜〜!(人波に押され、きりもみ状に回りながらフェードアウトする感じで)
----
Posted by しぞーか式。 at
21:44
│Comments(0)
2009年12月31日
小さな扉の向こうから。

昨日、大好きだったお店が10年の歴史を閉じた。
マスターが独立するためということで、発展的解消。

このお店、不思議なつくりになっていて、隣の割烹と、この小さな扉で繋がっている。
お酒はバーカウンターで出してくれるが、料理は、この小さな扉からメモを渡し、しばらくすると向こうの扉から料理がやってくる。


このお店、隣の割烹の大将が、当時アルバイトをしていたこちらのマスターを見初め、店を始めさせたのだという。わずか2年ほどの若いマスターに店を任せたのだから、よっぽど大将の気に入ったのだろう。
大将の思い切りのよさもすごいし、それに答えて10年店を守ってきたマスターもすごい。
お店は、最初からすごくスタイルがあって、居心地がよかった。
私はほとんどバーとしてしか使わなかったので、ちょっと申し訳なかったけど、マスターと音楽の話をするのがとても楽しくて、よくかよわせてもらった。
閉店プレゼントに、CDをあげた。



赤、黄、青の信号カラー。
10年間、ごちそうさまでした。。
では、Iマスター、次のお店で会いましょう。

2009年12月30日
久しぶり!な『暮しの手帳』
子供の頃、近所の図書館に行くのが好きだった。
一日4冊しか借りられないんだけど、夏休みとかは朝一番に図書館で江戸川乱歩ものとかを四冊目一杯借りてきて、夕方までに全部読んで、また4冊借りたりした。
そんなわけで、その木造の図書館は自分の遊び場みたいなものだった。貸し出し担当のおじさんにはいつも可愛がってもらったし、ここで、いろんな本を、とりあえず物怖じせずに開いてみることを学んだ。
2階のものおきになっている部屋には、(たぶん昔貸し出ししていたんだろう)ドーナツ盤があって、古いフォークやクラシックがたくさんあったのを思い出す。
こんな場所で知り合ったのが『暮しの手帳』。小学生には縁のない話ばかりだったが、結構気にいって、いつも読んでいた。
最近はとんとご無沙汰だったのだけど、先日、静岡の伊勢丹裏の喫茶店「OAK」で再び出会った。

久しぶりに会った『暮しの手帳』は、もう活版印刷ではなくなっていたようだけど、そして内容も少しずつアップデートされてはいたけど、相変わらずの落ち着いた空気を閉じ込めていた。

表紙を開くと、冒頭が編み物特集。宮本三郎の油絵だ。
いきなりグッとくるなあ。


私は編み物は全然できないのだけれど、実家が毛糸を扱っていたので、こういう頁はツボだ。

こんなふうに、新型の洗濯物干し、みたいなちょっとした暮らしの知恵コラムも健在だし、、、、、

もちろん、ちょっと気を抜けばびしっと叱られる「教養」もある。
一流のレストランでは、予約していないと席が空いていても断られることがある、とチクリと刺したあとで、「自分の好き嫌いや、食事の目的を知らせるとお店側もやりやすい」という、とても実用的なアドバイスが続く。
感心したのはこのコラム。

しゃれた英語エッセイの翻訳では定評のある常盤新平さんだけど、、、

「料理や食事の英語が難しい。短い囲み記事なのだが、十回以上も辞書を引く」なんて書いてあって、常盤さんでもそうなんだ、、と、ちょっと安心したりする。

藤森さんの影絵の本。こうした色使いや造本は、はっきりと「暮らしの手帳」色があって、なつかしくも美しい。
(ふと思ったけど、この写真って、本を⇒雑誌のために撮影して⇒その頁を私が接写、という入れ子構造ですね。いや、余談でした)
でも、もちろん新陳代謝もあって。

あらら、近田春夫せんせいじゃありませんか。
うーん、暮しの手帳、侮るべからず!
一日4冊しか借りられないんだけど、夏休みとかは朝一番に図書館で江戸川乱歩ものとかを四冊目一杯借りてきて、夕方までに全部読んで、また4冊借りたりした。
そんなわけで、その木造の図書館は自分の遊び場みたいなものだった。貸し出し担当のおじさんにはいつも可愛がってもらったし、ここで、いろんな本を、とりあえず物怖じせずに開いてみることを学んだ。
2階のものおきになっている部屋には、(たぶん昔貸し出ししていたんだろう)ドーナツ盤があって、古いフォークやクラシックがたくさんあったのを思い出す。
こんな場所で知り合ったのが『暮しの手帳』。小学生には縁のない話ばかりだったが、結構気にいって、いつも読んでいた。
最近はとんとご無沙汰だったのだけど、先日、静岡の伊勢丹裏の喫茶店「OAK」で再び出会った。

久しぶりに会った『暮しの手帳』は、もう活版印刷ではなくなっていたようだけど、そして内容も少しずつアップデートされてはいたけど、相変わらずの落ち着いた空気を閉じ込めていた。

表紙を開くと、冒頭が編み物特集。宮本三郎の油絵だ。
いきなりグッとくるなあ。


私は編み物は全然できないのだけれど、実家が毛糸を扱っていたので、こういう頁はツボだ。

こんなふうに、新型の洗濯物干し、みたいなちょっとした暮らしの知恵コラムも健在だし、、、、、

もちろん、ちょっと気を抜けばびしっと叱られる「教養」もある。
一流のレストランでは、予約していないと席が空いていても断られることがある、とチクリと刺したあとで、「自分の好き嫌いや、食事の目的を知らせるとお店側もやりやすい」という、とても実用的なアドバイスが続く。
感心したのはこのコラム。

しゃれた英語エッセイの翻訳では定評のある常盤新平さんだけど、、、

「料理や食事の英語が難しい。短い囲み記事なのだが、十回以上も辞書を引く」なんて書いてあって、常盤さんでもそうなんだ、、と、ちょっと安心したりする。

藤森さんの影絵の本。こうした色使いや造本は、はっきりと「暮らしの手帳」色があって、なつかしくも美しい。
(ふと思ったけど、この写真って、本を⇒雑誌のために撮影して⇒その頁を私が接写、という入れ子構造ですね。いや、余談でした)
でも、もちろん新陳代謝もあって。

あらら、近田春夫せんせいじゃありませんか。
うーん、暮しの手帳、侮るべからず!
タグ :暮らしの手帳
2009年12月29日
マジック アワー。

うちの居間には、午後の一瞬だけ、太陽の明かりが差し込む時間がある。
今日は、明かりがうまいことちゃぶ台の足に当たっていてきれいだったので記念写真。

足のみの特別出演は、もらっちゃ王(6歳男子)。
2009年12月28日
しつもん。

静岡にはボンヌールって名前のパン屋さんが多いんだけど、みんなコンセプトもメニューがちがう。
たとえば、この古庄店は、庶民的な惣菜パンや懐かしい感じのサンドイッチがおいしい。
しかもリーズナブル。

でも、浅間通りのお店はオーガニックな感じで値段もちょっと高め。
どういう歴史を経てこうなのか、すごく気になってる。
2009年12月27日
天使のはしご
雲の多い日、ふとした拍子で太陽が顔を出すことがある。
光が空から降り注ぐ様が天にかかるはしごのように見えるので、通称「天使のはしご」。
今日午後二時ごろに御前崎灯台辺りにいた人は、ひょっとしたら梯子を降りてくる天使を見たかもね。
光が空から降り注ぐ様が天にかかるはしごのように見えるので、通称「天使のはしご」。
今日午後二時ごろに御前崎灯台辺りにいた人は、ひょっとしたら梯子を降りてくる天使を見たかもね。
2009年12月26日
2009年12月26日
未確認ギラギラ物体
 今朝台所に発見。銀色のギラギラしたもの。
今朝台所に発見。銀色のギラギラしたもの。きのう確かに鳥の丸焼きがここに存在した、かすかなしるし。
といっても「本体」は私も昨夜、美味しく頂いていたのであった。
もらっちゃ王(5歳男子)は、気にいって、夕ごはんにもりもり食べていたらしい。
2009年12月25日
2009年12月24日
サンタさん三態(+1)
場所は静岡呉服町。
とある茶店が閉じたあと。
静まり返った店内で。
サンタが空からやってきた。

知らざあ言って聞かせましょう。
静岡名物8の字の。
横で見栄切る見慣れぬ貌は。
唐辛子サンタたあ、俺のこと。

一息入れたらこれから仕事、待っておいでよサンターズ。
かわい坊主と逢いたいけれど。
覚めては会われぬこの世の定め。
せめて眠れよ すやすやと。
背なのトナカイ鳴いている。

よっ日本一っ、ていうかむしろ世界一!!
てなわけで、呉服町の喫茶店、オークの、サンタさんたちも、今宵は大忙し、であろう。
あなたのところにもきっと来るはず。

とある茶店が閉じたあと。
静まり返った店内で。
サンタが空からやってきた。

知らざあ言って聞かせましょう。
静岡名物8の字の。
横で見栄切る見慣れぬ貌は。
唐辛子サンタたあ、俺のこと。

一息入れたらこれから仕事、待っておいでよサンターズ。
かわい坊主と逢いたいけれど。
覚めては会われぬこの世の定め。
せめて眠れよ すやすやと。
背なのトナカイ鳴いている。

よっ日本一っ、ていうかむしろ世界一!!
てなわけで、呉服町の喫茶店、オークの、サンタさんたちも、今宵は大忙し、であろう。
あなたのところにもきっと来るはず。

2009年12月23日
たああかい たあああかい。
昨日の妻の「小話」を書いていたら、昔、母がよく聞かせてくれたお気に入りの話を思い出した。
母が小学生の頃、近所にラジオの鉄塔があった。
母の故郷は、(そんなに市内からは離れていないけど)かつては田んぼが広がる農村だった。田んぼの中で、赤と白に塗り分けられた高い鉄塔は、とても目立っていただろう。
私も、子供の頃、鉄塔の先端に、編み笠みたいな形の金属がついていたのをうっすら憶えている。
さて、遠足かなにかで、母と友達は、その鉄塔に向かってどんどん歩いていた。
近づくにつれ、鉄塔もどんどん高くなっていく。
そこで、その友達は学校で習ったばかりの「俳句」を詠んだのだそうだ。
「たあかい たあかい てっとうだ」
そこで、母が、「それでは5,7,5になっていないから俳句じゃない」、と突っ込んだら、
「たああかい たああああかい てつとうだ」
とトンチで答えたらしい。
まあとにかく、母と友達はそんなバカ話をしつつ、鉄塔の先端を見上げながらどんどん近づいていった。
すると、友達は、そのまま上を向きすぎて、あおむけにコケてしまったという。
↑
ここ、笑いどころ!
この話、母に何回聞いたか忘れたが、この転ぶところを話すたびに、母がツボにはまって、笑ってしゃべれなくなっていた。
私たちは、その話もだけど、その母の姿がおかしくてみんなで笑っていたことを思い出す。
母が小学生の頃、近所にラジオの鉄塔があった。
母の故郷は、(そんなに市内からは離れていないけど)かつては田んぼが広がる農村だった。田んぼの中で、赤と白に塗り分けられた高い鉄塔は、とても目立っていただろう。
私も、子供の頃、鉄塔の先端に、編み笠みたいな形の金属がついていたのをうっすら憶えている。
さて、遠足かなにかで、母と友達は、その鉄塔に向かってどんどん歩いていた。
近づくにつれ、鉄塔もどんどん高くなっていく。
そこで、その友達は学校で習ったばかりの「俳句」を詠んだのだそうだ。
「たあかい たあかい てっとうだ」
そこで、母が、「それでは5,7,5になっていないから俳句じゃない」、と突っ込んだら、
「たああかい たああああかい てつとうだ」
とトンチで答えたらしい。
まあとにかく、母と友達はそんなバカ話をしつつ、鉄塔の先端を見上げながらどんどん近づいていった。
すると、友達は、そのまま上を向きすぎて、あおむけにコケてしまったという。
↑
ここ、笑いどころ!
この話、母に何回聞いたか忘れたが、この転ぶところを話すたびに、母がツボにはまって、笑ってしゃべれなくなっていた。
私たちは、その話もだけど、その母の姿がおかしくてみんなで笑っていたことを思い出す。
2009年12月23日
2009年12月22日
どっちでも行けます。
先週末、殿(中三女子。殿だけど女子)の、卒業記念写真を撮るということで伝馬町まで家族で行った。
さて、もろもろ終えて、妻の運転で立体駐車場を出る段になり、円形の大きな鉄板に車を載せた。
係のおじさん「どっちへ出ますか?」
この駐車場、出口が二つあり、行き先によって選べるようになっている。お客さんの返事次第で、車を向ける方向を変えるわけだ。
妻「どっちでもいいですよ(ニコリ)」
おじさんが困ったのを見て、妻はこうフォローした。
妻「右へ出たら◎街道だし、左へ出たら国道で、どっちでも帰れるので、どっちでもいいです(ニコリ)」
私は、おじさんの代わりに、
私「で、どっちへ出たいの?」
と思わず突っ込んでしまった。
さて、もろもろ終えて、妻の運転で立体駐車場を出る段になり、円形の大きな鉄板に車を載せた。
係のおじさん「どっちへ出ますか?」
この駐車場、出口が二つあり、行き先によって選べるようになっている。お客さんの返事次第で、車を向ける方向を変えるわけだ。
妻「どっちでもいいですよ(ニコリ)」
おじさんが困ったのを見て、妻はこうフォローした。
妻「右へ出たら◎街道だし、左へ出たら国道で、どっちでも帰れるので、どっちでもいいです(ニコリ)」
私は、おじさんの代わりに、
私「で、どっちへ出たいの?」
と思わず突っ込んでしまった。
2009年12月21日
2009年12月20日
【り】い【ん】か【ね】ーしょん、輪廻。
今日20日は静岡アートギャラリーの最終日。気になっていた方は急いでください!
というわけで、私も先日慌ててアートギャラリーへ向かった。
この展覧会は、10月から始まっている『「本」になった展覧会』と、11月から始まった『この場所で』の展覧会が、同時に12月20日に終わるという仕掛けになっている。
『本~』の方は、「本」をキーワードに、様々な作品を並べるという趣向。
紙の束である本、開くと新しい世界が広がる場所としての本、記憶を閉じ込める箱としての本、、、、など、それぞれのアーティストなりの「本」が並んでいる。
(この感想は、以前しぞーか式の「めくりめくって~頁間の迷宮へようこそ」で書いた。)
さて、これが面白かったので、『この場所で』展も見る気満々だった。ところが見れていなかったので、ずーっと落ち着かない想いをしていたのだった。
しかし、なんとか間にあって見ることができて、よかった。
『この場所で』展は、「かいこういちばん」さんも静岡アートギャラリーの,“ラストサムライ”を観てで触れておられる。
私が印象に残ったのは、まずは、牛の彫刻で知られる石上和弘さんの彫刻作品だった。
へその緒をつけたままの牛の子供3匹が、それぞれを尻尾を追う形で円形につながっている彫刻。
そして、5メートルはあるであろう、巨大なへその緒の彫刻。木彫だし、サイズも巨大なんだけど、へその緒のプリプリしたテクスチャーや、なんともいえないパステルホワイトの色合いが、不思議にリアルでもある。
ヘソの緒は、普段目にしないけれど実は命の誕生の瞬間に常に世界に現れ出るもの。なのに、世界に現れたときには、既に役割を終えているもの。そういうものに目をつけたところが面白く、強い作品になったと思う。
同時に展示されていた巨大なバス(というか荷車?)は、黄泉の国へ連れて行かれそうで、ちょっと恐いのだが、これも色は同じ黄色っぽいパステルホワイト。人一人が半身を入れられるぐらいの空間が車体に掘り込んであって、そこにすっぽりからだを沈めると、包まれている安心感と、どこに連れて行かれるのか判らないような恐さがないまぜになって、とても奇妙な心地よさを感じる。
最近流行の「オーガニック」、というキーワードでは零れ落ちてしまう、生命への畏れみたいなものも含めた存在感がある作品だった。
もう一つ、印象的だったのは、稲垣立男さんの、廃校になった小学校を、残された写真をもとに再現した作品。
たとえば。
図工で作った粘土工作のモノクロ写真がある。いかにも子供が作ったものらしく、ゆがんでいたり、ねじれていたりする。たぶん、記念に撮ったものだろうが、何十年前のものだから、よもやこの作品は残っていないだろう。
そして、その写真の隣には、写真どおりにそっくり再現された、ホンモノの粘土で作った工作が置かれている。
現存しない学校の、現存しない粘土の工作が、まさに目の前にある。
このほかにも、当時の小学校の見取り図や、黒板を再現したものなど(「みぎ」と書いた紙が黒板の右側に貼ってあったりして)、他人の記憶の中に片足を突っ込んだような、不思議な感覚がある。
見ていると、自分自身の小学校時代の記憶が作品に触発されてよみがえってくる。できごとの記憶だけでなく、鉛筆の黒鉛を舐めたときの味とか、木の手すりの手触りとか、そういうものが。
「ヘソの緒」の作品にしろ、「小学校」の作品にしろ、自分のそのままの記憶ではないものを触媒に、自分の記憶が際限なくつむぎだされる面白さ。記憶が、世界と作者と私の間で輪廻されていく。
静岡アートギャラリーもこれで一区切り。静岡市立美術館としての再スタートは来年だという。
この場所の次なる輪廻、期待しています。
というわけで、私も先日慌ててアートギャラリーへ向かった。
この展覧会は、10月から始まっている『「本」になった展覧会』と、11月から始まった『この場所で』の展覧会が、同時に12月20日に終わるという仕掛けになっている。
『本~』の方は、「本」をキーワードに、様々な作品を並べるという趣向。
紙の束である本、開くと新しい世界が広がる場所としての本、記憶を閉じ込める箱としての本、、、、など、それぞれのアーティストなりの「本」が並んでいる。
(この感想は、以前しぞーか式の「めくりめくって~頁間の迷宮へようこそ」で書いた。)
さて、これが面白かったので、『この場所で』展も見る気満々だった。ところが見れていなかったので、ずーっと落ち着かない想いをしていたのだった。
しかし、なんとか間にあって見ることができて、よかった。
『この場所で』展は、「かいこういちばん」さんも静岡アートギャラリーの,“ラストサムライ”を観てで触れておられる。
私が印象に残ったのは、まずは、牛の彫刻で知られる石上和弘さんの彫刻作品だった。
へその緒をつけたままの牛の子供3匹が、それぞれを尻尾を追う形で円形につながっている彫刻。
そして、5メートルはあるであろう、巨大なへその緒の彫刻。木彫だし、サイズも巨大なんだけど、へその緒のプリプリしたテクスチャーや、なんともいえないパステルホワイトの色合いが、不思議にリアルでもある。
ヘソの緒は、普段目にしないけれど実は命の誕生の瞬間に常に世界に現れ出るもの。なのに、世界に現れたときには、既に役割を終えているもの。そういうものに目をつけたところが面白く、強い作品になったと思う。
同時に展示されていた巨大なバス(というか荷車?)は、黄泉の国へ連れて行かれそうで、ちょっと恐いのだが、これも色は同じ黄色っぽいパステルホワイト。人一人が半身を入れられるぐらいの空間が車体に掘り込んであって、そこにすっぽりからだを沈めると、包まれている安心感と、どこに連れて行かれるのか判らないような恐さがないまぜになって、とても奇妙な心地よさを感じる。
最近流行の「オーガニック」、というキーワードでは零れ落ちてしまう、生命への畏れみたいなものも含めた存在感がある作品だった。
もう一つ、印象的だったのは、稲垣立男さんの、廃校になった小学校を、残された写真をもとに再現した作品。
たとえば。
図工で作った粘土工作のモノクロ写真がある。いかにも子供が作ったものらしく、ゆがんでいたり、ねじれていたりする。たぶん、記念に撮ったものだろうが、何十年前のものだから、よもやこの作品は残っていないだろう。
そして、その写真の隣には、写真どおりにそっくり再現された、ホンモノの粘土で作った工作が置かれている。
現存しない学校の、現存しない粘土の工作が、まさに目の前にある。
このほかにも、当時の小学校の見取り図や、黒板を再現したものなど(「みぎ」と書いた紙が黒板の右側に貼ってあったりして)、他人の記憶の中に片足を突っ込んだような、不思議な感覚がある。
見ていると、自分自身の小学校時代の記憶が作品に触発されてよみがえってくる。できごとの記憶だけでなく、鉛筆の黒鉛を舐めたときの味とか、木の手すりの手触りとか、そういうものが。
「ヘソの緒」の作品にしろ、「小学校」の作品にしろ、自分のそのままの記憶ではないものを触媒に、自分の記憶が際限なくつむぎだされる面白さ。記憶が、世界と作者と私の間で輪廻されていく。
静岡アートギャラリーもこれで一区切り。静岡市立美術館としての再スタートは来年だという。
この場所の次なる輪廻、期待しています。
2009年12月19日
いちごキノコ

今年のイチゴは甘い、と
大事に食べる姫(小3女子)。
それにしても…
今日は喉と節々が痛い。熱はないけど、とりあえず早く寝よう。
Posted by しぞーか式。 at
21:55
│Comments(0)
2009年12月18日
地動説、天動説
しっかりと木にロープがかけられていた。
近所の神社にて。

あー、倒れそうな木を支えてるんだな。
と思った、けど。

でもすぐに気づいた。
倒れそうなのは石の囲いのほうだな、きっと。
近所の神社にて。

あー、倒れそうな木を支えてるんだな。
と思った、けど。

でもすぐに気づいた。
倒れそうなのは石の囲いのほうだな、きっと。
Posted by しぞーか式。 at
04:00
│Comments(0)
2009年12月17日
2009年12月16日
モスラやモスラ

あっ、鉄塔に巨大な繭!

モスラが生まれる、かもね。
駿府公園のお堀沿い、NHK静岡にて。
ところで、静岡弁って語尾に「ら」をつけるんだけど、これが絶妙に怪獣の名前っぽい。
昔『5時ら』っていう情報番組もあったなあ。
さらにところで。
私は幼稚園の頃「グズラ」と呼ばれていた。
でも理由は教えてあげない。
今グズグズと幼稚園に出かけていった「もらっちゃ王」(5歳男子)にバレたらかっこ悪いからである。
2009年12月15日
ひねもす。
小学校の頃って、みんなが手を上げていると釣られてよく手を挙げてしまったものだ。
「この歌ってどんな意味だと思う?」と先生。
国語の授業でのことだった。
大概は他の子が当たるので油断していると、ここぞというところで、全然見当もつかない問題が当たってしまったりする。
この日もそんなマーフィの法則どおり、見事当たる。
困った挙句、わからないまま答えた。
「春の海に、ヒネモスがのたりのたりと浮いているところをうたっていると思います」
案の定、先生に「ヒネモスって何?」と切り替えされて、立ち往生してしまった。
ネタと思われても仕方がないが、ほんとうに事実である。
「春の海 ひねもす のたりのたりかな」蕪村
ちなみに、教科書的正答は、「春の海は 一日中 のたりのたりと波打っているなあ」、だと思う。
・・・・・・・・・
でも、ホントに珍獣「ヒネモス・ノタリ」を一瞬見かけたような気がする(でも確信はないことだなあ)、という歌だったら、どうしますか?
春の海 ヒネモス ノタリ のたりかな?
さて、先日、沼津に立ち寄ったとき、こんなカフェを見つけた。

『ひねもすCAFE』。

大正3年に建てられた石造りの蔵を改装したカフェだ。

古いつくりの蔵を大切に改装してある。
なんでも、昔は「ダンスホール」だったこともあったのだとか。
モボ、モガが集う場所だったのだろうか。
時は経って。
表通りから一本入った路地に、10年ほど使われずにほおって置かれていたのを、オーナーさんが友人たちと自力で修理して、今の状態にまで持っていったのだという。
大変な労力だ。そして、自分好みの場所を作りたいという強い思いと。
しかし、このカフェ、どこを見ても、全て絵になってしまう。




うーん、ユルさに隙がない、、、、、、っていうと違うな、「凛としてユルい」、かな。
この時のBGMは、原田郁子のソロアルバム、『ピアノ』。
完璧だ。

ひねもすCAFE
沼津市魚町20番地
営業時間
12:00~21:30(LO21:00)
定休日
月曜日・火曜日(祭日営業)
「この歌ってどんな意味だと思う?」と先生。
国語の授業でのことだった。
大概は他の子が当たるので油断していると、ここぞというところで、全然見当もつかない問題が当たってしまったりする。
この日もそんなマーフィの法則どおり、見事当たる。
困った挙句、わからないまま答えた。
「春の海に、ヒネモスがのたりのたりと浮いているところをうたっていると思います」
案の定、先生に「ヒネモスって何?」と切り替えされて、立ち往生してしまった。
ネタと思われても仕方がないが、ほんとうに事実である。
「春の海 ひねもす のたりのたりかな」蕪村
ちなみに、教科書的正答は、「春の海は 一日中 のたりのたりと波打っているなあ」、だと思う。
・・・・・・・・・
でも、ホントに珍獣「ヒネモス・ノタリ」を一瞬見かけたような気がする(でも確信はないことだなあ)、という歌だったら、どうしますか?
春の海 ヒネモス ノタリ のたりかな?
さて、先日、沼津に立ち寄ったとき、こんなカフェを見つけた。

『ひねもすCAFE』。

大正3年に建てられた石造りの蔵を改装したカフェだ。

古いつくりの蔵を大切に改装してある。
なんでも、昔は「ダンスホール」だったこともあったのだとか。
モボ、モガが集う場所だったのだろうか。
時は経って。
表通りから一本入った路地に、10年ほど使われずにほおって置かれていたのを、オーナーさんが友人たちと自力で修理して、今の状態にまで持っていったのだという。
大変な労力だ。そして、自分好みの場所を作りたいという強い思いと。
しかし、このカフェ、どこを見ても、全て絵になってしまう。




うーん、ユルさに隙がない、、、、、、っていうと違うな、「凛としてユルい」、かな。
この時のBGMは、原田郁子のソロアルバム、『ピアノ』。
完璧だ。

ひねもすCAFE
沼津市魚町20番地
営業時間
12:00~21:30(LO21:00)
定休日
月曜日・火曜日(祭日営業)