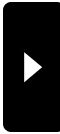2010年03月31日
京都ネイティヴ、になったつもり。

 京都最後の夜は、京都駅前の立ち飲み屋で。
京都最後の夜は、京都駅前の立ち飲み屋で。竹の子の焚いたんやおから、カレイの煮たの。お約束のメニューになぜか金沢の菊姫、富山の立山などこだわりの日本酒。
いやー、落ちつきます。
Posted by しぞーか式。 at
20:23
│Comments(0)
2010年03月30日
2010年03月29日
2010年03月28日
放課後に、こっそり。
気がついたら、2,3日前にこのブログも1周年を終えていました。
祝おうにも、まさにあとの祭り。
これからも、ぼちぼち続けていきますので、気が向いたらまた遊びにきてください。
さて、春の嵐の中で始まった、スノドカフェ『本日休講(その2)』に参加してきた。
清水の「出会い系」カフェ&ギャラリー、スノドカフェは、たくさんのおもしろい企画を連打している。音楽会あり、展覧会あり、また、講師をまねいての、アート関係の講義や討論会あり。
『本日休校』も、そうしたスノド新企画の一つ。これは、「講義が突然休講になってしまった時に、先生のいない場で学生が自由に話す」、という状況設定の下、「アート(にちょっとカスる)話ならなんでもあり」の、フリートーク企画だ。

天気のせいもあって、今回集まったのは7人(だったかな)。少人数の中で、あいかわらず濃い会話が進められた。
三々五々集まったメンバーが、気になるキーワードを、付箋紙に適当に書いていく。決まったテーマはなし。
普通の講義と違い、詳細なノートが取れていないのだけれど。
これは考えればあたりまえで、講師が一方的にしゃべっているのではなく、自分もその討議に参加しているからだ。
議論はたゆたう。
そして、頻繁で唐突な話題転換。
こんなものが面白いのか、と思われる方もいるかもしれないが、これが、実に面白いのだ。たぶん、付箋紙にキーワードを残して、それをチラ見しながら、話がいったりきたりするという流れが面白いのかもしれない。遠くへ拡散しそうになった話が、しばらく前に出ていたキーワードに呼び戻されて、急に話の見通しがよくなったりする。
まるでパンくずを落としながら森に分け入っていくヘンゼルとグレーテルみたいだ。

そういう長~い会話の後に、だんだん自分たちがなんの言葉を巡って話していたのか、あとで判ってくる感じが、これまたスリリングだった。
今回見えてきたのは、「ヴァキュラー」というキーワード。
ヴァナキュラー、というのは、かなり定義がめんどくさい言葉らしく、私も議論の中ではよくわからなかった。
いろんな意味があって、
語学用語・・・教師からしっかりと体系的に学んで「いない」ため、その土地の言葉に影響され変質した言葉。(ピジンとかクレオールみたいなもの??よくわかってません)
建築用語・・・土地の風土にフィットする固有の建築様式。先住民の住居など。
写真用語・・・美術作品という意図なく撮影されてきた写真。遺影とか、記念写真とか。
というわけで、上記の三つがともに「ヴァナキュラー」という言葉でくくられるのがまだぴんと来てないし、それぞれの分野での使われ方も、なんとなくクリアーに見えてこない。
いまだよくつかめていないのだけど、土地固有の、土着の、ということの意味を問い直し、アートの領域を広げるという動きの一つだと思う。
以前からスノドカフェでは「サイトスペシフィック」という概念がよく話題になっていた。これは、「静岡にいてアートは可能か」という、スノドカフェでは通奏低音のように奏でられるテーマとリンクしてしているからだ。
サイトスペシフィックというのは、やはり土地固有のものと結びつくのだけれども、普通言われるのは、その土地、その場所に置かれることを前提にして作られるアートをさす、作家目線の言葉。
一方、ヴァナキュラーは、解釈者の方からもともとあったものに意味づけを与えるための言葉といえる。
サイトスペシフィックも、ヴァナキュラーも、土地、風土と言うものに深く結びついた概念であることは共通している。
今回の『本日休講』は、
「朝カフェの意味」・・・いつもと違う時間に、いつものことをやる
「ガンダム茶会」
旋回教徒とテクノの関係とか
http://www.youtube.com/watch?v=S45OJnQp6mI&feature=player_embedded
十分に話が拡散して、とても楽しかった。でも、中でいちばん驚きうなづいたのは、中央で活躍する静岡出身者は、どこかたがが外れている、という話。

おだやかな気候風土の中で、愛されて育ったせいか、グロテスクなもの、奇妙なものへ物怖じせずに近づいていくところがみんな共通しているのではないか、という話。
これは、指摘されてはっとした。
静かな狂気、いや、しぞーかな狂気、か。
これはまさにそうかも知れない。
祝おうにも、まさにあとの祭り。
これからも、ぼちぼち続けていきますので、気が向いたらまた遊びにきてください。
さて、春の嵐の中で始まった、スノドカフェ『本日休講(その2)』に参加してきた。
清水の「出会い系」カフェ&ギャラリー、スノドカフェは、たくさんのおもしろい企画を連打している。音楽会あり、展覧会あり、また、講師をまねいての、アート関係の講義や討論会あり。
『本日休校』も、そうしたスノド新企画の一つ。これは、「講義が突然休講になってしまった時に、先生のいない場で学生が自由に話す」、という状況設定の下、「アート(にちょっとカスる)話ならなんでもあり」の、フリートーク企画だ。

天気のせいもあって、今回集まったのは7人(だったかな)。少人数の中で、あいかわらず濃い会話が進められた。
三々五々集まったメンバーが、気になるキーワードを、付箋紙に適当に書いていく。決まったテーマはなし。
普通の講義と違い、詳細なノートが取れていないのだけれど。
これは考えればあたりまえで、講師が一方的にしゃべっているのではなく、自分もその討議に参加しているからだ。
議論はたゆたう。
そして、頻繁で唐突な話題転換。
こんなものが面白いのか、と思われる方もいるかもしれないが、これが、実に面白いのだ。たぶん、付箋紙にキーワードを残して、それをチラ見しながら、話がいったりきたりするという流れが面白いのかもしれない。遠くへ拡散しそうになった話が、しばらく前に出ていたキーワードに呼び戻されて、急に話の見通しがよくなったりする。
まるでパンくずを落としながら森に分け入っていくヘンゼルとグレーテルみたいだ。

そういう長~い会話の後に、だんだん自分たちがなんの言葉を巡って話していたのか、あとで判ってくる感じが、これまたスリリングだった。
今回見えてきたのは、「ヴァキュラー」というキーワード。
ヴァナキュラー、というのは、かなり定義がめんどくさい言葉らしく、私も議論の中ではよくわからなかった。
いろんな意味があって、
語学用語・・・教師からしっかりと体系的に学んで「いない」ため、その土地の言葉に影響され変質した言葉。(ピジンとかクレオールみたいなもの??よくわかってません)
建築用語・・・土地の風土にフィットする固有の建築様式。先住民の住居など。
写真用語・・・美術作品という意図なく撮影されてきた写真。遺影とか、記念写真とか。
というわけで、上記の三つがともに「ヴァナキュラー」という言葉でくくられるのがまだぴんと来てないし、それぞれの分野での使われ方も、なんとなくクリアーに見えてこない。
いまだよくつかめていないのだけど、土地固有の、土着の、ということの意味を問い直し、アートの領域を広げるという動きの一つだと思う。
以前からスノドカフェでは「サイトスペシフィック」という概念がよく話題になっていた。これは、「静岡にいてアートは可能か」という、スノドカフェでは通奏低音のように奏でられるテーマとリンクしてしているからだ。
サイトスペシフィックというのは、やはり土地固有のものと結びつくのだけれども、普通言われるのは、その土地、その場所に置かれることを前提にして作られるアートをさす、作家目線の言葉。
一方、ヴァナキュラーは、解釈者の方からもともとあったものに意味づけを与えるための言葉といえる。
サイトスペシフィックも、ヴァナキュラーも、土地、風土と言うものに深く結びついた概念であることは共通している。
今回の『本日休講』は、
「朝カフェの意味」・・・いつもと違う時間に、いつものことをやる
「ガンダム茶会」
旋回教徒とテクノの関係とか
http://www.youtube.com/watch?v=S45OJnQp6mI&feature=player_embedded
十分に話が拡散して、とても楽しかった。でも、中でいちばん驚きうなづいたのは、中央で活躍する静岡出身者は、どこかたがが外れている、という話。

おだやかな気候風土の中で、愛されて育ったせいか、グロテスクなもの、奇妙なものへ物怖じせずに近づいていくところがみんな共通しているのではないか、という話。
これは、指摘されてはっとした。
静かな狂気、いや、しぞーかな狂気、か。
これはまさにそうかも知れない。
2010年03月27日
食いてし止まん

 今日はなぜか渋谷区神宮前の「こどもの城」にもらっちゃ王と遊びに来た。
今日はなぜか渋谷区神宮前の「こどもの城」にもらっちゃ王と遊びに来た。なかなか楽しくて、このことはいずれ書くつもりだけど…。
今日はiPhoneから投稿なので軽めに、メシネタを
。
毎週土曜は、隣の国連の建物(?)の前のスペースで青空市場が開かれているらしい。でも、食材はざっと見るだけで片付けて、また性懲りもなくカレーですよ。
味はそこそこながら、いい天気でオープンな場所で食べたのでよしとします。
ちなみにもらっちゃ王が食べたホットドッグもイマイチ…。ちょい討ち死に気味。
----
Posted by しぞーか式。 at
21:30
│Comments(0)
2010年03月26日
カレーなる日々(その2)
まだまだ続く、静岡カレー行脚。
藤枝の『ルチ バングラディシュ レストラン』

藤枝駅前から歩いて5分ぐらいのところにある、バングラディシュカレーのお店。
この日食べたのはトマトカレー。私もこの1か月でだんだん辛さに耐性ができてきたので、「辛め」でオーダーしてみた。
この、もちもちしたナンみたいな「ルティ」をつけていただく。

バングラディシュらしく(いや、ホントは行ったことはないんだけど)、さすがにスパイシー。
だけど、辛さで味がわからないということはない。
トマトの酸味とか、唐辛子以外のスパイスの味わいはしっかりわかる。
お店の人はフレンドリーに、辛さを気にしてくれたけど、大丈夫、すごくおいしいし、堪能できましたよ。
お店の張り紙、
「スローなお店です。お忙しい方もゆっくりおあがりください」(うろ覚え)
が、お店のゆる~い感じをうまく物語っている。
ルチ バングラディッシュ レストラン
RUCHI BANGLADESH RESTAURANT
藤枝市駅前1-8-22
11:30~14:30、17:00~21:30
続いては、磐田のインドカレー、『ナマステ』。

これは、店内の張り紙。あらためて「カレー」といわれると、なんか笑える。

磐田市見付3409-1
11:00~14:30 17:00~22:00
月曜休み
最後は、静岡市内に戻ってきて、スリランカカレーの『サヒル17』。

右側が豆のカレー、左側が鳥のカレーのコンビネーション。まんなかの黄色いのは、、、、ごめんなさい、忘れてしまった。
スリランカというと、猛烈に辛いカレーなんじゃないかという先入観があったんだけど(そして、中には実際にもんのすごく辛いカレーもあるんだけど)、実際に食べてみると、ほとんど辛さを感じないものからはじまって、様々なグレードがある。

ちなみに、この豆はほとんど辛くない。そして、様々なスパイスが渾然となって、どんなものがはいっているのか、味で察することはできかなった。でも、美味しい。そして、なんだか元気になって幸せな気分になる。
店主のサジットさんによれば、スリランカは日本よりもずっと野菜が豊富らしい。20種類のスパイスをその食材にあわせて使いわけるそうで、レシピも数え切れないほどあるという。さすがスパイスの国。
『サヒル17』
葵区古庄4丁目2-13(上土保育園の隣)
毎週木曜日及び毎月第1土曜日のみ
上記は、休業日ではなく、営業日。つまり、月に5日ぐらいしか営業していないので、ご注意ください。
ふう。
かけあしで、この一月で食べたカレーを紹介してみた。
いつもの調子で一軒についてのレビューをこってり書くのもいいんだけど、こうして概観してばーっと書き連ねることで、かえって見えてくることもあるなあ。
ひとくちにカレーと言っても、いろんな国があり、それぞれに様々な食材で作るカレーがある。シェフも様々なバックグラウンドを持っている。同じ国のシェフでも、専門が違えば全然違う料理を作るわけで(たとえば、日本のそば職人ととんかつ職人が違うように・・・)極端に言えば「全部違う」「みんな違う」としかいえない。
でも。
静岡からは1日、2日、へたすれば3日かかる人もいる。お国の政情でそもそも気軽に帰れない人も。そんな人たちが、たまたま静岡に住んで、たまたまレストランをやっている。
そんなお店に、静岡にいながらこんなにたくさん出会えるというのは、かなり素敵なことだと思う。
余談なんだけど、経営者の方やシェフと話すと、本業は別に持っている人も多いことに驚いた。つまり、「珍しい料理で一儲けしてやれ!」みたいな感覚はあんまりなくて、自分の国の料理を(食材や調理器具の制約はあるにせよ)なるべく食べて欲しいという思いを持っている人ばっかりなのだった。
まずは自分で食べたいから始めた、という人も何人かいた。
そういうふうに、自分の国のごはんを食べたいと思う気持ちはとっても素直だし、そういうお店は食べる側としても信じられる、と思う。
最後に、オマケ情報。
写真はないけど、さらに駆け足でいくつか紹介します…
トルコ料理の『カフェ イスタンブール』。
上足洗に去年できたお店だ。
カレーとは言いにくいんだけど、スパイスたっぷりの肉をヨーグルトをつけてさっぱり頂く感じが新鮮だった。
『カフェ イスタンブール』
静岡市葵区上足洗44-3
ランチ 11:00〜14:00ディナー 17:00〜21:00
そして、ミャンマー料理の『バガン』。
北街道に去年の暮れにできたお店。お得なバイキングで、いろいろ味わえる。
単品も実は充実しているので、最初はバイキングで、そして一通り楽しんだら単品で注文してみると、結構楽しいと思う。
"Bagan"
葵区太田町31-1(北街道沿い)
Lunch 11:30-14:00 Dinner 17:00-23:00 無休
・・・・しかし、上記の2軒もまさにそうなんだけど、広い意味での北街道周辺の外国レストランはすごいことになっている。
数も多いし、味もバリエーションも充実している。
こんど、時間ができたら、アラキタ(アラウンド北街道)のレストランレビューを、気合入れてやってみるかな。
ホントに最後に、余談の余談。カレーの食べ歩きをしていてふと思ったことがある。
どうしても、エスニックは「辛くて食べられない」「辛いけどおいしい」みたいに、辛いという部分が感想の軸になってしまうのだけれど。
でも、唐辛子以外のスパイスにも目を向ける(舌を向ける?)のが楽しむコツかもしれない。
辛いのが苦手な人は、無理せず「辛さ抑え目で」と注文すればいいのだとおもう。
そして、そのぶん食材の味や、唐辛子以外の様々なスパイスやハーブをしっかり味わう方が数段楽しいんではないかと、最近思い始めている。
藤枝の『ルチ バングラディシュ レストラン』

藤枝駅前から歩いて5分ぐらいのところにある、バングラディシュカレーのお店。
この日食べたのはトマトカレー。私もこの1か月でだんだん辛さに耐性ができてきたので、「辛め」でオーダーしてみた。
この、もちもちしたナンみたいな「ルティ」をつけていただく。

バングラディシュらしく(いや、ホントは行ったことはないんだけど)、さすがにスパイシー。
だけど、辛さで味がわからないということはない。
トマトの酸味とか、唐辛子以外のスパイスの味わいはしっかりわかる。
お店の人はフレンドリーに、辛さを気にしてくれたけど、大丈夫、すごくおいしいし、堪能できましたよ。
お店の張り紙、
「スローなお店です。お忙しい方もゆっくりおあがりください」(うろ覚え)
が、お店のゆる~い感じをうまく物語っている。
ルチ バングラディッシュ レストラン
RUCHI BANGLADESH RESTAURANT
藤枝市駅前1-8-22
11:30~14:30、17:00~21:30
続いては、磐田のインドカレー、『ナマステ』。

これは、店内の張り紙。あらためて「カレー」といわれると、なんか笑える。

磐田市見付3409-1
11:00~14:30 17:00~22:00
月曜休み
最後は、静岡市内に戻ってきて、スリランカカレーの『サヒル17』。

右側が豆のカレー、左側が鳥のカレーのコンビネーション。まんなかの黄色いのは、、、、ごめんなさい、忘れてしまった。
スリランカというと、猛烈に辛いカレーなんじゃないかという先入観があったんだけど(そして、中には実際にもんのすごく辛いカレーもあるんだけど)、実際に食べてみると、ほとんど辛さを感じないものからはじまって、様々なグレードがある。

ちなみに、この豆はほとんど辛くない。そして、様々なスパイスが渾然となって、どんなものがはいっているのか、味で察することはできかなった。でも、美味しい。そして、なんだか元気になって幸せな気分になる。
店主のサジットさんによれば、スリランカは日本よりもずっと野菜が豊富らしい。20種類のスパイスをその食材にあわせて使いわけるそうで、レシピも数え切れないほどあるという。さすがスパイスの国。
『サヒル17』
葵区古庄4丁目2-13(上土保育園の隣)
毎週木曜日及び毎月第1土曜日のみ
上記は、休業日ではなく、営業日。つまり、月に5日ぐらいしか営業していないので、ご注意ください。
ふう。
かけあしで、この一月で食べたカレーを紹介してみた。
いつもの調子で一軒についてのレビューをこってり書くのもいいんだけど、こうして概観してばーっと書き連ねることで、かえって見えてくることもあるなあ。
ひとくちにカレーと言っても、いろんな国があり、それぞれに様々な食材で作るカレーがある。シェフも様々なバックグラウンドを持っている。同じ国のシェフでも、専門が違えば全然違う料理を作るわけで(たとえば、日本のそば職人ととんかつ職人が違うように・・・)極端に言えば「全部違う」「みんな違う」としかいえない。
でも。
静岡からは1日、2日、へたすれば3日かかる人もいる。お国の政情でそもそも気軽に帰れない人も。そんな人たちが、たまたま静岡に住んで、たまたまレストランをやっている。
そんなお店に、静岡にいながらこんなにたくさん出会えるというのは、かなり素敵なことだと思う。
余談なんだけど、経営者の方やシェフと話すと、本業は別に持っている人も多いことに驚いた。つまり、「珍しい料理で一儲けしてやれ!」みたいな感覚はあんまりなくて、自分の国の料理を(食材や調理器具の制約はあるにせよ)なるべく食べて欲しいという思いを持っている人ばっかりなのだった。
まずは自分で食べたいから始めた、という人も何人かいた。
そういうふうに、自分の国のごはんを食べたいと思う気持ちはとっても素直だし、そういうお店は食べる側としても信じられる、と思う。
最後に、オマケ情報。
写真はないけど、さらに駆け足でいくつか紹介します…
トルコ料理の『カフェ イスタンブール』。
上足洗に去年できたお店だ。
カレーとは言いにくいんだけど、スパイスたっぷりの肉をヨーグルトをつけてさっぱり頂く感じが新鮮だった。
『カフェ イスタンブール』
静岡市葵区上足洗44-3
ランチ 11:00〜14:00ディナー 17:00〜21:00
そして、ミャンマー料理の『バガン』。
北街道に去年の暮れにできたお店。お得なバイキングで、いろいろ味わえる。
単品も実は充実しているので、最初はバイキングで、そして一通り楽しんだら単品で注文してみると、結構楽しいと思う。
"Bagan"
葵区太田町31-1(北街道沿い)
Lunch 11:30-14:00 Dinner 17:00-23:00 無休
・・・・しかし、上記の2軒もまさにそうなんだけど、広い意味での北街道周辺の外国レストランはすごいことになっている。
数も多いし、味もバリエーションも充実している。
こんど、時間ができたら、アラキタ(アラウンド北街道)のレストランレビューを、気合入れてやってみるかな。
ホントに最後に、余談の余談。カレーの食べ歩きをしていてふと思ったことがある。
どうしても、エスニックは「辛くて食べられない」「辛いけどおいしい」みたいに、辛いという部分が感想の軸になってしまうのだけれど。
でも、唐辛子以外のスパイスにも目を向ける(舌を向ける?)のが楽しむコツかもしれない。
辛いのが苦手な人は、無理せず「辛さ抑え目で」と注文すればいいのだとおもう。
そして、そのぶん食材の味や、唐辛子以外の様々なスパイスやハーブをしっかり味わう方が数段楽しいんではないかと、最近思い始めている。
2010年03月25日
カレーなる日々
このひと月はほんとによくカレーを食べた。
なんだか憑かれでもしたように。
というわけで(どういうわけだ?)写真を撮っていたものだけ、ざっと並べてみる。
改めて見ても、いやあ、よく食べたなあ、これが。
まずは、長谷通りの『六文銭』。

野菜カレー、たしか700円。
カレーのマイブームの始まりはここだったような気がする。
野菜たっぷり、トマトはとりわけたっぷり、をよく煮込んでとろとろにしてある。ひき肉の入った、薬膳風キーマカレー、みたいな感じ。学割があるのも、なんとなく長谷通りに似合っている。
『六文銭』
静岡市葵区東草深町4−15
木曜休み
続いて『オーク』のコンビネーションカレー。

『オーク』は、日替わりで20種類ぐらいのカレーがある。この日はコンビネーションカレーを注文した。左側が豆のカレー、中央にターメリックライス、右側はたぶん鶏肉カレーだったと思う。

豆のカレーの上にちょこんと乗っているのは生の唐辛子。でも、青い香りが快くて、おもわずみんな食べてしまった。このあたりで、なんかカレースイッチが入ってしまった。
『OAK(オーク)』
葵区両替町1丁目5-7 チサンマンション1F
平日・土曜 9:00 ~ 20:00、日曜・祝日10:00 ~ 20:00
水曜休み

続いては、『タージマハール』のマトンのカレー。ターメリックライスとチャイがついて850円だったらしい。(今ネットで調べてみた)
親切に辛さを聞いてくれるので、ちょっと辛めに挑戦してみたが、大丈夫、おいしく最後まで頂けた。味は普通だけど、駐車場有、サーブも早いし、気楽にカレーを食べられる場所としてはなかなかよい。
このあたりで、からだがスパイスを求めて止まらなくなったのかな。辛いのを食べると、頭がボーっとなるのだけど、それがきもちいいのだ。
TAJ MAHAL (タージマハル)
葵区沓谷5-12-9
11:00~15:00 17:00~22:00
無休
そして再び『オーク』(!)

たぶん豆とひき肉のカレーだと思う。このあたりの記憶と、再訪したタイミングは全く覚えていない。
スパイス効果かな?
オークはカレーブームの前から月に1,2回は行っているので、二回目の登場となった。
マンダレーレストランのチキンカレー。

こちらは、静岡では数少ないミャンマー料理店。

馬渕のヤマダデンキの近く。お店がこういう外観なので、ちょっと心配になってしまうかもしれない。
でも心配ご無用。
他のエスニック料理より日本人には食べやすいと思う。ミャンマー料理は、スパイスは(比較的)ひかえめ、ココナッツもあまり使わない。食材のうまみを多目の油に染み出させていただくという特徴があるらしい。

鳥のカレー。
ランチはメニューが少ないが、夜はいろいろ食べられるらしく、落ち着いたら夜に行ってみたいお店の一つ。ミャンマー風豚足というのがすごく気になっている。
でも、ちょっと交通が不便なのが難点なんだよな。
ミャンマー料理マンダレーレストラン
静岡市駿河区馬渕2-9-15
11:00~14:30、17:00~21:00
火曜定休
そろそろ書きつかれてきたが、まだ道はなかば。
明日に続く、ということにしよう。
いや、この一ヶ月、とにかく、カレーばっかり食べていたのだった。
なんだか憑かれでもしたように。
というわけで(どういうわけだ?)写真を撮っていたものだけ、ざっと並べてみる。
改めて見ても、いやあ、よく食べたなあ、これが。
まずは、長谷通りの『六文銭』。

野菜カレー、たしか700円。
カレーのマイブームの始まりはここだったような気がする。
野菜たっぷり、トマトはとりわけたっぷり、をよく煮込んでとろとろにしてある。ひき肉の入った、薬膳風キーマカレー、みたいな感じ。学割があるのも、なんとなく長谷通りに似合っている。
『六文銭』
静岡市葵区東草深町4−15
木曜休み
続いて『オーク』のコンビネーションカレー。

『オーク』は、日替わりで20種類ぐらいのカレーがある。この日はコンビネーションカレーを注文した。左側が豆のカレー、中央にターメリックライス、右側はたぶん鶏肉カレーだったと思う。

豆のカレーの上にちょこんと乗っているのは生の唐辛子。でも、青い香りが快くて、おもわずみんな食べてしまった。このあたりで、なんかカレースイッチが入ってしまった。
『OAK(オーク)』
葵区両替町1丁目5-7 チサンマンション1F
平日・土曜 9:00 ~ 20:00、日曜・祝日10:00 ~ 20:00
水曜休み

続いては、『タージマハール』のマトンのカレー。ターメリックライスとチャイがついて850円だったらしい。(今ネットで調べてみた)
親切に辛さを聞いてくれるので、ちょっと辛めに挑戦してみたが、大丈夫、おいしく最後まで頂けた。味は普通だけど、駐車場有、サーブも早いし、気楽にカレーを食べられる場所としてはなかなかよい。
このあたりで、からだがスパイスを求めて止まらなくなったのかな。辛いのを食べると、頭がボーっとなるのだけど、それがきもちいいのだ。
TAJ MAHAL (タージマハル)
葵区沓谷5-12-9
11:00~15:00 17:00~22:00
無休
そして再び『オーク』(!)

たぶん豆とひき肉のカレーだと思う。このあたりの記憶と、再訪したタイミングは全く覚えていない。
スパイス効果かな?
オークはカレーブームの前から月に1,2回は行っているので、二回目の登場となった。
マンダレーレストランのチキンカレー。

こちらは、静岡では数少ないミャンマー料理店。

馬渕のヤマダデンキの近く。お店がこういう外観なので、ちょっと心配になってしまうかもしれない。
でも心配ご無用。
他のエスニック料理より日本人には食べやすいと思う。ミャンマー料理は、スパイスは(比較的)ひかえめ、ココナッツもあまり使わない。食材のうまみを多目の油に染み出させていただくという特徴があるらしい。

鳥のカレー。
ランチはメニューが少ないが、夜はいろいろ食べられるらしく、落ち着いたら夜に行ってみたいお店の一つ。ミャンマー風豚足というのがすごく気になっている。
でも、ちょっと交通が不便なのが難点なんだよな。
ミャンマー料理マンダレーレストラン
静岡市駿河区馬渕2-9-15
11:00~14:30、17:00~21:00
火曜定休
そろそろ書きつかれてきたが、まだ道はなかば。
明日に続く、ということにしよう。
いや、この一ヶ月、とにかく、カレーばっかり食べていたのだった。
2010年03月24日
2010年03月23日
御奈良についての一考察
さいきん、うちのもらっちゃ王はおならに夢中である。
今日などは、お風呂の中で、「これから泡が出るからね」と、予告。みんなが止めるのにもかかわらず、しっかりブクブクと泡を出していた。
先日、もらっちゃ王作の『くまのうんちはくさい』という絵本を紹介したが、「なぜ小さい子供はこんなにシモのお話に過剰反応するのかなあと思うんだけど。
自分のからだから出るもの、そして、自分以外になってしまうもの。そんなものが気になるのかね。
今日などは、お風呂の中で、「これから泡が出るからね」と、予告。みんなが止めるのにもかかわらず、しっかりブクブクと泡を出していた。
先日、もらっちゃ王作の『くまのうんちはくさい』という絵本を紹介したが、「なぜ小さい子供はこんなにシモのお話に過剰反応するのかなあと思うんだけど。
自分のからだから出るもの、そして、自分以外になってしまうもの。そんなものが気になるのかね。
2010年03月22日
テレビの新しい見方。
先ほどまで、ネットでNHKスペシャルの「裏番組」を見ていた。
といっても、この説明ではわからないと思うので、ざっと説明してみる。
最近、ネットの技術も進歩して、すごく簡単に個人レベルで生中継ができるようになった。これまでも映像を配信するしくみはあったのだけど(たとえばYOUTUBE)、それが生でできるというわけ。
その中でも気を吐いているのがUSTREAM。なんでもない飲み会を中継したりすることもできるわけで、この場で自分の日常生活を放送する人が出てきた。
でも、ただの飲み会を中継しても誰も見ない。そんなわけで、誰がいる、どこの場面にカメラを置くかがとても大切になってくる。
とまあ、こういう前提で、今日あったのが、テレビを見ながらダラダラ話す「飲み会」を、USTREAMで中継する、というもの。ホリエモンとか、津田さんとかのウエブの世界での有名人5人が集まって、ビールを飲みながらだらだらと話をするという「番組」だ。
今回の企画は、NHKスペシャルで、『激震!マスメディア』という番組を生放送している、まさにそのウラで、そのテレビの感想をいろいろしゃべるというものだった。
視聴者は、テレビを見つつ、ウエブの生中継も見つつ、ついでにツイッターをしている人は、みんながツイッターでつぶやくという、、もう、テレビ2系統、ツイッター2系統ということで、どれもながら見しかできないという、ものすごい状況。
で、さて、このネット生中継のUSTREAM。
http://www.ustream.tv/channel/ptf-live1
「いくらなんでも、これはだらだらしすぎじゃない」、という津田さんの提案で、急遽、テレビが終わった後に同じメンバーで対談を続けることになって。
・・・で、今も続いているんです。夜の11:55現在で、8586人が視聴している。
もちろん、テレビの視聴者と比べれば全然少ないんだけど。
見ている自分にも熱気が伝わるし、津田さんが対談継続の提案をしたのも、きっとこのメディア、この放送スタイルをなんとか伸ばしていきたいという思いなんだろうな。
今回のネット対談とは直接関係ないんだけど、たとえば、スポーツ中継とか、ドラマとかの「副音声」として、こういうウラ対談があると、かなり楽しい。
とにかく、メディア環境があれば、ぜひ見て欲しい、USTREAM+TWITTERの面白さ。
まだまだ対談は続いているんだけど、とりあえずこのへんで。
といっても、この説明ではわからないと思うので、ざっと説明してみる。
最近、ネットの技術も進歩して、すごく簡単に個人レベルで生中継ができるようになった。これまでも映像を配信するしくみはあったのだけど(たとえばYOUTUBE)、それが生でできるというわけ。
その中でも気を吐いているのがUSTREAM。なんでもない飲み会を中継したりすることもできるわけで、この場で自分の日常生活を放送する人が出てきた。
でも、ただの飲み会を中継しても誰も見ない。そんなわけで、誰がいる、どこの場面にカメラを置くかがとても大切になってくる。
とまあ、こういう前提で、今日あったのが、テレビを見ながらダラダラ話す「飲み会」を、USTREAMで中継する、というもの。ホリエモンとか、津田さんとかのウエブの世界での有名人5人が集まって、ビールを飲みながらだらだらと話をするという「番組」だ。
今回の企画は、NHKスペシャルで、『激震!マスメディア』という番組を生放送している、まさにそのウラで、そのテレビの感想をいろいろしゃべるというものだった。
視聴者は、テレビを見つつ、ウエブの生中継も見つつ、ついでにツイッターをしている人は、みんながツイッターでつぶやくという、、もう、テレビ2系統、ツイッター2系統ということで、どれもながら見しかできないという、ものすごい状況。
で、さて、このネット生中継のUSTREAM。
http://www.ustream.tv/channel/ptf-live1
「いくらなんでも、これはだらだらしすぎじゃない」、という津田さんの提案で、急遽、テレビが終わった後に同じメンバーで対談を続けることになって。
・・・で、今も続いているんです。夜の11:55現在で、8586人が視聴している。
もちろん、テレビの視聴者と比べれば全然少ないんだけど。
見ている自分にも熱気が伝わるし、津田さんが対談継続の提案をしたのも、きっとこのメディア、この放送スタイルをなんとか伸ばしていきたいという思いなんだろうな。
今回のネット対談とは直接関係ないんだけど、たとえば、スポーツ中継とか、ドラマとかの「副音声」として、こういうウラ対談があると、かなり楽しい。
とにかく、メディア環境があれば、ぜひ見て欲しい、USTREAM+TWITTERの面白さ。
まだまだ対談は続いているんだけど、とりあえずこのへんで。
タグ :USTREAM
2010年03月21日
唐辛子で国境越え

 静鉄ストアで辛み調味料をさがしていたら、その名も「デスソース」というのを見つけた。
静鉄ストアで辛み調味料をさがしていたら、その名も「デスソース」というのを見つけた。ボトルの形はなんとなくタバスコ似。でも、デカデカとドクロがあしらわれたラベルが、危険なほどの辛さをアピール。
辛さ別に四本セットで、結構いい値段はしたんだけど、いつも棚に並んでいるし、静鉄ストアの定番っぽい感じがしたのでそんなに外れはないだろうと、挑戦してみることにした。
それぞれ、『アフターデスソース(死後のソース)』とかいって、律儀に不吉な名前がついている。
そしてオマケは骸骨のキーホルダー。ちなみに、これはもらっちゃ王と一個ずつもらった。
タバスコもそうだけど、こういう辛い系の調味料は、メキシコとかコスタリカとか、異境のイメージをまとっている。それも、なんとなくだけど国境の南な感じ。
とりあえず、一番辛いのは後回しにして、二番目に辛いのから挑戦。お皿に一滴だけ滴らして、ちょっと味見すると…
辛いよ、これ。舌にびりびり来るし、食べると
顔が熱くなって、鼻水がどんどん出てきて止まらなくなる感じ。期待通りの、いや期待以上の辛さだった。
まだ一番辛いボトルは開けていなくて、これもいつかは味見をするんだろうけど、きっと最後まで使いきれない予感がするなあ。かなりキケンな調味料である。
そう思うと、ハイソで高級イメージがある静鉄ストアに、こんな荒馬みたいな調味料が並んでいること自体、かなりにすごいことのような気がしてきた。
話は変わるが…。
私はここのところ、なんでこんなに辛いものが食べたいんだろう。
辛いのを求める気持ちって、辛いものを食べた後のフィジカルな体の変化も楽しんでいる気がする。
舌はヒリヒリ、体はポカポカ。頭が辛さでぼーっとする感じ。ひょっとしたら脳内にはドーパミンとか出まくっているのかも知れないな。いい音楽を聞いた時の反応とそっくりだなあ。
ということは、ここんところの私は、そういうふうに気分を変えて、大げさにいえば世界が違って見えるクスリが欲しくて辛い食べ物を食べまくっていたのだろうか。
そうか。そうすると、
辛さを求める気持ちって、やっぱり究極にはここではないどこかへの越境願望なのかもしれないな。
Posted by しぞーか式。 at
22:58
│Comments(0)
2010年03月20日
2010年03月19日
語り得ぬもの。
「見る人それぞれが、それぞれに感じればいいんです」
たとえば、現代アートの解説書とか、アートについての入門的な講演会とか、、、そういう場で、「アートを見るときは肩の力を抜けば楽しいですよ」というニュアンスをこめて、よく言われる言葉だ。
でも、気持ちはわかるんだけど、私は昔からこの言い回しがすごくいやだった。
見た人がそれぞれの文脈で勝手に感じるだけでアート鑑賞が終わりなら、誰かと作品の感想を語っても深まらないし、作品の背景を知ったり、制作の現場に思いをはせたり、、、、、そんな、アートを見る楽しみの4分の3ぐらいが、「それぞれに感じればいい」と言われた瞬間に、失せてしまうような気がするのだ。
なにより、この言葉は、語る側にも、見る側にも、それ以上アートについて知ろう・深めようとする気をなくさせる、魔法のフレーズなので。
さて、一部ではずいぶん話題になっていた本らしいのだけど、今日ようやく読み終えた。
『音楽の聴き方』岡田暁生(2009年 中公新書)
岡田さんの本は、『西洋音楽史』(中公新書)を読んで、とても面白かったのでこの作品も買ってみたのだけど、いやいや、『音楽の聴き方』は、それをはるかに超えるすごい本だった。
何がすごいって、「語り得ぬものについては沈黙「してはいけない」」という、その態度である。
ヴィトゲンシュタインという哲学者の有名なフレーズに、「語り得ぬものについては沈黙しなくてはならない」というのがある。「語れないことについては語らない」という節度をもつべきだ、ということで、音楽やアートなどを語るときにも時々引用される。
(この言葉を聴くと、いつも孔子の「怪力乱神を語らず」を連想するのだけど、それはまた別の話。)
確かに音楽はもともと言葉にはできないわけで、だから「音楽をあれこれ理屈で語っちゃ興ざめだ」と言われると一瞬正しいような気もしてしまうのだけど、岡田さんは、だからって沈黙しちゃいけない、と主張する。
岡田さんによれば、特にクラシック音楽は、批評と音楽が車輪の両輪みたいなもので、作者も言語化を前提に作ってきたし、また批評することでその音楽はより深く理解できる、というのだ。
「聴いて楽しければいいんです」、という言い回しには、落とし穴がある。音楽には、必ず語学で言う文法みたいなものが必ずあるし、演奏家は当然それを前提に演奏をしている。
だから、聞き手がそのルールを知っているか否かでは、楽しみ方が全然違ってくるのだ。
何も知らずにポンと聴くだけでも楽しいんだけど、知ればさらに楽しいというあたりまえのことが、豊富な事例を挙げて例証されている。
読んでいると、この本の射程はクラシック音楽だけでなく、ジャズ、ワールドミュージックや、アート、ファッションにまで届くことがわかる。
アートやファッションや、、、、、自分の好きなものがもっと好きになるきっかけになるかもしれない、刺激的な本だ。
たとえば、現代アートの解説書とか、アートについての入門的な講演会とか、、、そういう場で、「アートを見るときは肩の力を抜けば楽しいですよ」というニュアンスをこめて、よく言われる言葉だ。
でも、気持ちはわかるんだけど、私は昔からこの言い回しがすごくいやだった。
見た人がそれぞれの文脈で勝手に感じるだけでアート鑑賞が終わりなら、誰かと作品の感想を語っても深まらないし、作品の背景を知ったり、制作の現場に思いをはせたり、、、、、そんな、アートを見る楽しみの4分の3ぐらいが、「それぞれに感じればいい」と言われた瞬間に、失せてしまうような気がするのだ。
なにより、この言葉は、語る側にも、見る側にも、それ以上アートについて知ろう・深めようとする気をなくさせる、魔法のフレーズなので。
さて、一部ではずいぶん話題になっていた本らしいのだけど、今日ようやく読み終えた。
『音楽の聴き方』岡田暁生(2009年 中公新書)
岡田さんの本は、『西洋音楽史』(中公新書)を読んで、とても面白かったのでこの作品も買ってみたのだけど、いやいや、『音楽の聴き方』は、それをはるかに超えるすごい本だった。
何がすごいって、「語り得ぬものについては沈黙「してはいけない」」という、その態度である。
ヴィトゲンシュタインという哲学者の有名なフレーズに、「語り得ぬものについては沈黙しなくてはならない」というのがある。「語れないことについては語らない」という節度をもつべきだ、ということで、音楽やアートなどを語るときにも時々引用される。
(この言葉を聴くと、いつも孔子の「怪力乱神を語らず」を連想するのだけど、それはまた別の話。)
確かに音楽はもともと言葉にはできないわけで、だから「音楽をあれこれ理屈で語っちゃ興ざめだ」と言われると一瞬正しいような気もしてしまうのだけど、岡田さんは、だからって沈黙しちゃいけない、と主張する。
岡田さんによれば、特にクラシック音楽は、批評と音楽が車輪の両輪みたいなもので、作者も言語化を前提に作ってきたし、また批評することでその音楽はより深く理解できる、というのだ。
「聴いて楽しければいいんです」、という言い回しには、落とし穴がある。音楽には、必ず語学で言う文法みたいなものが必ずあるし、演奏家は当然それを前提に演奏をしている。
だから、聞き手がそのルールを知っているか否かでは、楽しみ方が全然違ってくるのだ。
何も知らずにポンと聴くだけでも楽しいんだけど、知ればさらに楽しいというあたりまえのことが、豊富な事例を挙げて例証されている。
読んでいると、この本の射程はクラシック音楽だけでなく、ジャズ、ワールドミュージックや、アート、ファッションにまで届くことがわかる。
アートやファッションや、、、、、自分の好きなものがもっと好きになるきっかけになるかもしれない、刺激的な本だ。
2010年03月18日
伝わることの奇跡
昔、学校で心理学の授業を取っていた。その中で猿に言葉を教える実験の話があったことを、最近ふと思い出した。
うろ覚えなのだけど…。
青い色をしたものを見せた時に猿が青のボタンを押すと餌をやる。青いものなら何でも可。
そして、赤い色をしたものを見せた時に赤のボタンを押すと餌をやる。すると、猿は、だんだん正しいボタンを押すようになる。
こうして、猿は赤と青という抽象概念を学んだ、というわけ。
「この実験を進めていけば、人間が言葉を習得する秘密がわかる」と言われると、ワクワクした。
なるほど、こうやって人間も言葉を覚えるのかな、とは思ったんだけど。
思ったんだけど、どうしても聞きたくなって聴いてしまった。
「せつない」とか、「愛しい」とか。人生で何度もない経験を表す言葉を、人はどうやって習得するんだろう。
そして、その言葉がすごく確かな実在感を持っているのって、いくら考えても不思議だ。
そもそも、自分がいつこういう言葉を覚えたのかが不思議でしょうがない。
うろ覚えなのだけど…。
青い色をしたものを見せた時に猿が青のボタンを押すと餌をやる。青いものなら何でも可。
そして、赤い色をしたものを見せた時に赤のボタンを押すと餌をやる。すると、猿は、だんだん正しいボタンを押すようになる。
こうして、猿は赤と青という抽象概念を学んだ、というわけ。
「この実験を進めていけば、人間が言葉を習得する秘密がわかる」と言われると、ワクワクした。
なるほど、こうやって人間も言葉を覚えるのかな、とは思ったんだけど。
思ったんだけど、どうしても聞きたくなって聴いてしまった。
「せつない」とか、「愛しい」とか。人生で何度もない経験を表す言葉を、人はどうやって習得するんだろう。
そして、その言葉がすごく確かな実在感を持っているのって、いくら考えても不思議だ。
そもそも、自分がいつこういう言葉を覚えたのかが不思議でしょうがない。
Posted by しぞーか式。 at
21:23
│Comments(0)
2010年03月17日
影踏まない遊び

公園の柵の影が芝生に落ちでいた。
もらっちゃ王が歩きながら怪しい動きをしてる、と思ったら、影を踏まないようにぴょんぴょんしながら歩いていた。
昔、よくやったなあ。
この影を踏んだら負け、って
遊び。
Posted by しぞーか式。 at
23:59
│Comments(1)
2010年03月16日
2010年03月15日
Wな日曜日


昨日は芝川町の富士錦酒蔵の蔵開きに、もらっちゃ王と2人で行ってきた。
昨日書いた自動販売機の話も、その道中にあったことだった。
いやあ、それにしても楽しいイベントだった。そもそも、あの人数(去年の数字だが、主催者発表は12000人)の酒好き
が、全国から芝川に集うことが素晴らしい。
もらっちゃ王が勝手に動き回るので、そこに気を取られて、正直なところ完全にイベントを味わい尽くせたとは言えないのだけれど、これだけの人数を毎年さばいてきた自信も伺える、堂々とした運営だと思った。
食べ物屋台あり、試飲という名の振る舞い酒あり。足りない人にはお酒を売るブースもある。
そして、訪れる人たちも「こなれている」。
自分たちでブルーシートや椅子を持ち込み、料理も適当に持ち込んで、自然体でお酒を飲んでいる。
酔っ払ってシートに寝ている人たちも多数。
始末の悪い酔っ払いも、中にはいるんだろうけど、なんかPEACEな感じで、トラブルも見かけなかった。
これ、五十代のための野外音楽フェス(まあ音楽はないけどね)なのかもしれん、と、結構真剣に思った。
なんか、ここでうまくコラボして面白いこと出来ないかなあ。
二枚目の写真は、もらっちゃ王が出店で買ってご満悦の、仮面ライダーダブルの食器セット。500円で王がこれだけ喜んでくれるんなら安いもんである。
もらっちゃ王にとっては、この日はダブルのお皿を買った日、として記憶に残るはずである。
Posted by しぞーか式。 at
20:43
│Comments(4)
2010年03月14日
機械のおなか
 もらっちゃ王と駅のホームにて。
もらっちゃ王と駅のホームにて。お茶を買おうと思っていたら、ちょうど自販機の補充が始まってしまった。
もらっちゃ王は、買うつもりだったジュースのことも忘れて、おにいさんたちの詰め替え作業をじーっと見ていた。
なんてことをしている間に電車が来てしまい、結局もらっちゃ王はジュースを買えずじまい。
でも、もらっちゃ王は、自動販売機のおなかの中が見られたのが嬉しかったらしく、電車の中でもしばらくはその話をしていた。
----
もらっちゃ王的には、身近なモノの中身を見れたこともさることながら、あの箱からとめどなくジュースが出てくるんじゃなくて、きちんと補充してるんだってことが面白かったらしい。
もらっちゃ王には有意義な二分間だったかな。
Posted by しぞーか式。 at
22:45
│Comments(3)
2010年03月13日
電子的整理整頓
今しがた、やっとiTunesに入れている音楽ファイルの整理が終わった。というか、まだやることはあるんだけど、とりあえずひと段落着いた。
で、ふと時計を見るともう日が変わってしまう!
せっかくいい天気だったというのに、一日画面に向かっていてしまった。もらっちゃ王(5歳男子)を講演にも連れて行けなかったし、、、、。
よし、明日、天気がよければ、外に遊びに行くぞ!
なんていうわけで、ずーっと気になっていたパソコンの中のファイル整理はなんとか終わったものの、部屋のほうの整理整頓はこれからじゃないか、、、、。
現実世界の整理整頓も、ぼちぼちがんばらなきゃね。
で、ふと時計を見るともう日が変わってしまう!
せっかくいい天気だったというのに、一日画面に向かっていてしまった。もらっちゃ王(5歳男子)を講演にも連れて行けなかったし、、、、。
よし、明日、天気がよければ、外に遊びに行くぞ!
なんていうわけで、ずーっと気になっていたパソコンの中のファイル整理はなんとか終わったものの、部屋のほうの整理整頓はこれからじゃないか、、、、。
現実世界の整理整頓も、ぼちぼちがんばらなきゃね。
2010年03月12日
3月12日の記事
連日仕事の打ち上げがつづき、今日もいい感じで酔っ払い。
昨日は映画バグダッド カフェを見てきた。これも二十年を経ての再見ということで、最近なんかそんなのばっかりである。
今回は、割とシビアに見ちゃったかな。
映像美、というだけでは、映画一本は支えきれないということに、ちょっと面白みを感じた。
やっぱり、リバイバルという売りに、少し鈍感になってきたのかな。
昨日は映画バグダッド カフェを見てきた。これも二十年を経ての再見ということで、最近なんかそんなのばっかりである。
今回は、割とシビアに見ちゃったかな。
映像美、というだけでは、映画一本は支えきれないということに、ちょっと面白みを感じた。
やっぱり、リバイバルという売りに、少し鈍感になってきたのかな。
Posted by しぞーか式。 at
23:59
│Comments(0)


 京都を旅して
京都を旅して


 もらっちゃ王いわく、「バナナの花」。
もらっちゃ王いわく、「バナナの花」。