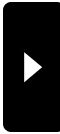2010年05月31日
2010年05月30日
2010年05月29日
まよなかのほんやさん
昨日、草薙の戸田書店が今月で閉店することを書いた。
この情報を知るそもそものきっかけは、私が愛読している平野雅彦さんのサイト『平野雅彦なら、こう考える』の「脳内探訪」でのこんな告知。
静岡で始まった新しい動きなので、なんとか空気にだけでも触れたい・・・のだけれど、その日は出張で結局22時過ぎに静岡到着。まあ、30分ぐらいでも見られればいいや、と思って、とりあえず草薙の戸田書店に到着したのが22時30分。
絵本コーナーでの坐講が終わって、書店の棚めぐりツアーがまさに始まろうというタイミングだった。
昨日アップした戸田書店の天井や壁の写真は、実はこのとき撮ったものだ。

というわけで、夜もふけて、本来ならしまっているはずの書棚の周りを、講師たちの話を聞きながら参加者がとりかこむ。この日は本当に終わりの部分しか聞けていないので私には書く資格がないかもしれないけど、それでも面白かった断片をいくつかメモしておこう。
書店店長の市原健太さんの、「雑誌は客の視線を誘導するように並べる」「本は30冊ぐらいのかたまりとして見ている」という視点。
本の分類記号の話。
本の分類記号は、図書館でよく見る分類方法のほかにもたくさんあるということ。たとえば、本の裏表紙に印刷されている、C+4ケタの数字。これも分類記号なんだとか。
そして、本の分類は当然内容によるもの、となんとなく思ってきたのだけど、実は出版社の「この本はこう売りたい」という意向を反映している部分も大きい、とか。
出版社は本を作る編集の人より営業の発言力が強く、営業が部数を決めてしまうので、編集や作家が「これは絶対売れる」と盛り上がっても、初版の部数が少なすぎて結局売れない、ということも多いとか。
いくら書店が「この本を置きたい」と思っても、出版社の意向が強いので回してれない本がある、とか。
20坪の書店ではやっていけないので、どんどん書店は大型化している、とか。

(すいません、人の写っている写真はこれしか撮っていませんでした)
私なら、20坪で書店をやるならどうするかなあ。
5坪は売れ筋の雑誌を置いて、5坪はモノクロの写真集の専門店、10坪は立ち飲みカフェ、ってのはどうだろう。
この情報を知るそもそものきっかけは、私が愛読している平野雅彦さんのサイト『平野雅彦なら、こう考える』の「脳内探訪」でのこんな告知。
静岡で始まった新しい動きなので、なんとか空気にだけでも触れたい・・・のだけれど、その日は出張で結局22時過ぎに静岡到着。まあ、30分ぐらいでも見られればいいや、と思って、とりあえず草薙の戸田書店に到着したのが22時30分。
絵本コーナーでの坐講が終わって、書店の棚めぐりツアーがまさに始まろうというタイミングだった。
昨日アップした戸田書店の天井や壁の写真は、実はこのとき撮ったものだ。

というわけで、夜もふけて、本来ならしまっているはずの書棚の周りを、講師たちの話を聞きながら参加者がとりかこむ。この日は本当に終わりの部分しか聞けていないので私には書く資格がないかもしれないけど、それでも面白かった断片をいくつかメモしておこう。
書店店長の市原健太さんの、「雑誌は客の視線を誘導するように並べる」「本は30冊ぐらいのかたまりとして見ている」という視点。
本の分類記号の話。
本の分類記号は、図書館でよく見る分類方法のほかにもたくさんあるということ。たとえば、本の裏表紙に印刷されている、C+4ケタの数字。これも分類記号なんだとか。
そして、本の分類は当然内容によるもの、となんとなく思ってきたのだけど、実は出版社の「この本はこう売りたい」という意向を反映している部分も大きい、とか。
出版社は本を作る編集の人より営業の発言力が強く、営業が部数を決めてしまうので、編集や作家が「これは絶対売れる」と盛り上がっても、初版の部数が少なすぎて結局売れない、ということも多いとか。
いくら書店が「この本を置きたい」と思っても、出版社の意向が強いので回してれない本がある、とか。
20坪の書店ではやっていけないので、どんどん書店は大型化している、とか。

(すいません、人の写っている写真はこれしか撮っていませんでした)
私なら、20坪で書店をやるならどうするかなあ。
5坪は売れ筋の雑誌を置いて、5坪はモノクロの写真集の専門店、10坪は立ち飲みカフェ、ってのはどうだろう。
2010年05月28日
本屋さんに捧ぐ
(5月29日記。
改めて読み返すとすごく読みにくいエントリーだったので、かなり改稿しました)

昔、『ベルリン天使の詩』という映画があった。
この映画に、巨大な図書館が登場する。高い天井、広いフロアを囲む回廊。私のおぼろげな記憶では、円筒形に吹き抜けた大きな図書館で、壁は全て書棚になっていて、2階にあたる部分はぐるりと回廊になっていたように思う。(もしかしたら、図書館のディテールは別の映画と混同している気もする。)
そして、この図書館は天使たちのたまり場みたいになっていて、2階の手すりに腰掛けたり、黙読する人間のとなりにじっと立っていたりする。んで、天使たちはみんなおじさんなのだ。

(写真はイメージです(笑)。)
さて、映画では、静かなはずのこの図書館に、ささやき声のようなものが満ちている。人間が黙読する音が、天使たちには音になってさんざめいている。たしか、天使が耳を寄せると、その人が黙読しながら何を考えているのかも聞こえてきたのではなかったかな。
考えてみれば、図書館というのは、膨大な過去が本という形でひとところに蓄積されている場所だ。そして、訪れる人間はそれぞれ全く違うことを考えながら本に向かい合っているわけで、天使たちも面白いからついつい訪れてしまうのだろうか。

草薙の戸田書店が今月で店を閉じる。
本が集まり、人が集まる場所であることは、図書館も書店も同じ。この天井は、どれだけの囁きを受け止めてきたのだろうか。もしかしたらここにも天使たちがいて、私たちを見下ろしているのかもしれない。

「音楽は終わると空に上り、二度ととらえることはできない。」
〜エリック ドルフィー〜
「音楽が終わったら
灯りを消して」
〜ジム モリソン(ドアーズ)〜
では、書店という場所が終わる時、私たちは何をすればいい?
私は、膨大な本の前に立つと、自分は一生かかってもこの全てを読めないんだなと思って、なんだか呆然とすることがある。でも、そういう気持ちにさせるのが書店という空間のいいところ。本が別世界への扉なら、書店は、その別世界がいかにたくさんあるのか知る場所なのだ。
前途茫洋、ああボーヨー、ボーヨー。
(たぶん明日に続く。)
改めて読み返すとすごく読みにくいエントリーだったので、かなり改稿しました)

昔、『ベルリン天使の詩』という映画があった。
この映画に、巨大な図書館が登場する。高い天井、広いフロアを囲む回廊。私のおぼろげな記憶では、円筒形に吹き抜けた大きな図書館で、壁は全て書棚になっていて、2階にあたる部分はぐるりと回廊になっていたように思う。(もしかしたら、図書館のディテールは別の映画と混同している気もする。)
そして、この図書館は天使たちのたまり場みたいになっていて、2階の手すりに腰掛けたり、黙読する人間のとなりにじっと立っていたりする。んで、天使たちはみんなおじさんなのだ。

(写真はイメージです(笑)。)
さて、映画では、静かなはずのこの図書館に、ささやき声のようなものが満ちている。人間が黙読する音が、天使たちには音になってさんざめいている。たしか、天使が耳を寄せると、その人が黙読しながら何を考えているのかも聞こえてきたのではなかったかな。
考えてみれば、図書館というのは、膨大な過去が本という形でひとところに蓄積されている場所だ。そして、訪れる人間はそれぞれ全く違うことを考えながら本に向かい合っているわけで、天使たちも面白いからついつい訪れてしまうのだろうか。

草薙の戸田書店が今月で店を閉じる。
本が集まり、人が集まる場所であることは、図書館も書店も同じ。この天井は、どれだけの囁きを受け止めてきたのだろうか。もしかしたらここにも天使たちがいて、私たちを見下ろしているのかもしれない。

「音楽は終わると空に上り、二度ととらえることはできない。」
〜エリック ドルフィー〜
「音楽が終わったら
灯りを消して」
〜ジム モリソン(ドアーズ)〜
では、書店という場所が終わる時、私たちは何をすればいい?
私は、膨大な本の前に立つと、自分は一生かかってもこの全てを読めないんだなと思って、なんだか呆然とすることがある。でも、そういう気持ちにさせるのが書店という空間のいいところ。本が別世界への扉なら、書店は、その別世界がいかにたくさんあるのか知る場所なのだ。
前途茫洋、ああボーヨー、ボーヨー。
(たぶん明日に続く。)
2010年05月27日
2010年05月26日
2010年05月25日
2010年05月24日
ラーメンとガクラン

ラーメン通の友人に勧められて、評判のラーメンを食べてきた。
このラーメンはすごくおいしかったのだけど、私は正直言ってそんなにラーメン好きではない。特に、最近のラーメンは。それは、なんとなく、スペック主義、みたいなのが仄見えるからだ。
昔、中学生だった頃、不良っぽい学生服(いわゆる「ガクラン」)のカタログを見るのが好きだった。
詰襟のエリが、グレードによってどんどん高くなっていき、いちばん高い(=ワルい)制服だと顔が半分ぐらい隠れるどでかいエリだったのとか。あと、裏地に龍とか虎とかの刺繍がついていたり。「ドカン」とかいう名前の土管のようにひたすら太いズボンとか。
当時、学校で抜き打ち服装検査みたいなのがあった。私はごくごく標準的なズボンをはいていたので(自分で変わった学生服を着ることには全く興味がなかった)、よく友人が、「ちょっと貸して」と、服装検査の間だけ、私とズボンを履き替えたりしていた。そうして履いてみると、ズボンの片っ方に両足が入るぐらいの太いズボンだったので、実際履いて見るとズボンの中で足が泳ぐ。すごく新鮮な履きごごちだったのを思い出す。
中でも笑ったのが、タック入りズボン。タックというのは、ズボンの腰の辺りに余裕をつけるためのプリーツ(?)なんだけど、当時学校の決まりではタックなしか1タックまでしか許されていなかった。そうなると、当然、タックの数が多いほどワルいズボンということになる。
んで、12タック(24本のプリーツが入っている)のズボン、なんてものがあって、そこまでいくと袴と言うか、プリーツスカートみたいになっていたのだった。
このあたり、スペック主義の陥穽というか、数字で他を引き離そうとすると、どんどん服として超自然的なものになっていくわけである。
、、、、。
いや、全てのラーメンが「12タック」みたいにガラパゴス進化していると言いたいわけではないし、そういう超自然的な努力をしたラーメンがおいしくないということでもない。
いや、正直な話、実際においしいことも多いのだから。
でも、どうも、魚粉を◎グラム使ったり、◎日煮込んだトンコツだったり、◎を入れた(入れない)麺だったり、、、、そういう、クレジットが先行すると、食べるときもそのクレジットを「確認する」姿勢で食べざるを得ないのが残念な気がするのだ。
こういうスペック主義のものは、エクセル処理に向いている。
スープや麺や、温度やチャーシューなどなどをパラメータで記録することができるし、場所、価格をあわせればデータベースへの収まりがたいへんによい。というか、むしろそういう風に楽しむものだという気すらする。このあたり、ワイン通ととても通じるものがあると思う。
ラーメンという「ウツワ」が、そういう様々な工夫を受け入れて、それぞれおいしく味わわせてしまう、おくの深い「ウツワ」だということなのだろうけど、とりあえず私はそれには乗りたくないな、という、、、、。
なんだか、今日はおじさんの愚痴になってしまった。
2010年05月23日
雨にも負けず。
もらっちゃ王の友達が書いた自動車の絵。

先日、雨に降られたあと、てっきり流されているだろうと思ったら、しっかり車は残っていた。誇らしげなもらっちゃ王。
(この日の夕方には流れてしまったけど)

先日、雨に降られたあと、てっきり流されているだろうと思ったら、しっかり車は残っていた。誇らしげなもらっちゃ王。
(この日の夕方には流れてしまったけど)
2010年05月22日
お泊り。

今晩は、姫(小四女子)ともらっちゃ王(5歳男子)が、友達の家にお泊りの日。
夕食も子供たちで作るらしい。写真はそのために姫が書き留めたカレーのレシピ。
書いたのはいいんだけど、ちょっとシンプル過ぎるんじゃない?
さっき、そのお宅にパジャマを届けたら、もらっちゃ王は大興奮であった。じゃあ、おやすみ!
2010年05月21日
仮面ライダー!…じゃないよ

静岡伊勢丹に、虚無でギャルソン、いや Comme des Garcons のBlackが登場。
仮面ライダーブラックじゃないが、かなり強そうである。
写真を見ると、ごっつい指輪をたくさんつけた指をあわせていて、なんだか変身しそうだ。
6月5日から一週間の限定。
----
ブラックは、いわばコムデギャルソンの入門ブランド。
ちょっと昔の名作デザインも含めてギャルソンの
エッセンスが比較的お安く楽しめる、はず。
最近物欲ミニマムの私を突き動かすものがあるか、楽しみ。
2010年05月20日
2010年05月19日
スリー。

偶然というか、必然というか。
朝は松屋でトマトカレー、昼はアローイアロイでタイ風グリーンカレー。
そして自宅でもカレーで、体内カレー指数100パーセント。
唐辛子で頭クラクラ、鼻ズルズル、目ウルウル。
2010年05月19日
2010年05月18日
2010年05月17日
2010年05月16日
5月16日の記事
今日もあと20分ほどで終わるんだけど、何を書こうかな。まだネタが決まってないとさすがにどうするか悩む。
うーん、しかたない、あの話にするか。
こないだ新幹線に乗っていたとき、なんかシンナー臭いな、まさかマニキュアじゃないだろうし、と思ったら、本当に五十歳ぐらいの女性が自然にマニキュアを塗っていてびっくりしたことがあった。
二三列離れて気づいたぐらいなので、近くの人はたまらなかったと思う。
見た目は特に派手でもない、
ごく普通の、ディスイズ日本のおばさん、みたいな人。
それだけに、すごくインパクトがあった。
今日はこれまで。お後がよろしいようで。
うーん、しかたない、あの話にするか。
こないだ新幹線に乗っていたとき、なんかシンナー臭いな、まさかマニキュアじゃないだろうし、と思ったら、本当に五十歳ぐらいの女性が自然にマニキュアを塗っていてびっくりしたことがあった。
二三列離れて気づいたぐらいなので、近くの人はたまらなかったと思う。
見た目は特に派手でもない、
ごく普通の、ディスイズ日本のおばさん、みたいな人。
それだけに、すごくインパクトがあった。
今日はこれまで。お後がよろしいようで。







 青い矢印の先をご覧ください、緑のrでございま〜す。
青い矢印の先をご覧ください、緑のrでございま〜す。
 ん?ふーん。
ん?ふーん。 柚木駅のモンドリアン。
柚木駅のモンドリアン。







 熱海の駅前。フツーの商店街に、ポツンと、温泉。
熱海の駅前。フツーの商店街に、ポツンと、温泉。