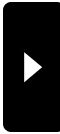2009年07月31日
2009年07月30日
雲の生まれるところ

三保の海水浴場でたくさん遊んで、、、、

遊びつかれた頭でドライブしていたら、三保半島の先端から雲が生まれている。
その、雲が生まれるところへドライブ。
この満足感、何と似ているんだろう???
子供の頃、身体が冷え切るまでプールで遊んで、プールから上がって、厚いコンクリートの上で横になる。
耳をコンクリートに着けると、入っていた水が「じわー」っと出てきて。
からだ全体が暖かなものにくるまれたような安心感。
気持ちよかった。
2009年07月30日
2009年07月29日
カポエイラという「場」、そして目眩について
以前、カポエイラを一度だけ体験した事がある。
カポエイラというのは、ブラジルで発達した武術、、、、おっと、武術でもあり、舞踏でもある、というもの。
ブラジルの奴隷たちはいざというときの腕を磨きたい。でも、暴動を恐れる支配者たちは、あからさまに「武術」を練習していると、必ず弾圧しにくる。そこで、これは踊りだ、ということにして、練習を積み、洗練されていったのが現在のカポエイラということらしい。
実際、踊りとも格闘技とも言いがたい。しかし、その「場」の持つ独特の昂揚感は、中毒性がある。
二人の戦い手を囲むように観客が車座になり、うたを歌う。そして、パンディロ(タンバリンみたいな楽器)やアタバキ(縦長のドラム)、ビリンバウ(この楽器は一口では説明しにくい、、、)などの伴奏で演技が進む。演者同士もアドリブの応酬があり、さらに演技と演奏も相互に煽りあって、車座の中は常にゆるやかな、時に烈しい緊張感が持続していく。この音楽も、おなかの底がもやもやムラムラしてくるような、不思議な土着的な力を潜ませている。
文章にしてもなかなか伝わらないのだけれども、生で見れば、その昂揚感は実感してもらえると思う。
さて、そのカポエイラ。
とにかく回転技が多い。宙返りしたり、横回りしたり、時にはブレイクダンスのように頭を支点にしてぐるりと回ったり、、、、。
日常生活では、こんな風に回転することはめったにない。それだけに、ちょっとだけ体験しても、目が回ってしまう、のだが。ちょっと練習をしてみると、自分の周りの世界と、その中で回っている自分の位置関係がおぼろげに見えてきて、その空間感覚が面白いのだ。自分がぐるりと回っていても、それに対して世界はずっしりとそこにあることが実感できる。
世界のずっしり感が実感できるというか、自分が回転するからこそ、世界が見える。
ぶらんこ。
そう、子どものころ、ぶらんこに何度も繰り返し乗った、あの時の感覚に近いかもしれない。
ロジェカイヨワの「めまい」
カポエイラというのは、ブラジルで発達した武術、、、、おっと、武術でもあり、舞踏でもある、というもの。
ブラジルの奴隷たちはいざというときの腕を磨きたい。でも、暴動を恐れる支配者たちは、あからさまに「武術」を練習していると、必ず弾圧しにくる。そこで、これは踊りだ、ということにして、練習を積み、洗練されていったのが現在のカポエイラということらしい。
実際、踊りとも格闘技とも言いがたい。しかし、その「場」の持つ独特の昂揚感は、中毒性がある。
二人の戦い手を囲むように観客が車座になり、うたを歌う。そして、パンディロ(タンバリンみたいな楽器)やアタバキ(縦長のドラム)、ビリンバウ(この楽器は一口では説明しにくい、、、)などの伴奏で演技が進む。演者同士もアドリブの応酬があり、さらに演技と演奏も相互に煽りあって、車座の中は常にゆるやかな、時に烈しい緊張感が持続していく。この音楽も、おなかの底がもやもやムラムラしてくるような、不思議な土着的な力を潜ませている。
文章にしてもなかなか伝わらないのだけれども、生で見れば、その昂揚感は実感してもらえると思う。
さて、そのカポエイラ。
とにかく回転技が多い。宙返りしたり、横回りしたり、時にはブレイクダンスのように頭を支点にしてぐるりと回ったり、、、、。
日常生活では、こんな風に回転することはめったにない。それだけに、ちょっとだけ体験しても、目が回ってしまう、のだが。ちょっと練習をしてみると、自分の周りの世界と、その中で回っている自分の位置関係がおぼろげに見えてきて、その空間感覚が面白いのだ。自分がぐるりと回っていても、それに対して世界はずっしりとそこにあることが実感できる。
世界のずっしり感が実感できるというか、自分が回転するからこそ、世界が見える。
ぶらんこ。
そう、子どものころ、ぶらんこに何度も繰り返し乗った、あの時の感覚に近いかもしれない。
ロジェカイヨワの「めまい」
2009年07月28日
いろ、いろいろ。
スノドカフェでの「いろ」の写真展、行きたかったなあ。
平野先生の記事を読むにつけ。
色覚の問題って、とても面白いと思っているので、今日はその話をしてみよう。
色って、かなり特殊な存在だと思うのだ。相互認識において。
たとえば、色弱の人に、一般的な色覚の人が出会ったと考えてみて欲しい。
私には苦もなく区別がつく色が、彼には区別がつかない。
おんなじ色に見える、ようだ。
じゃあ、「彼にはなぜこんなに違う二つの色が、おんなじに見えるんだろう」。
でも一方で、色弱のひとはこう思っているかもしれない。
「僕には同じに見える一つの色が、彼にはなんで違って見えるんだろう」。
これは、視力が弱くてよく見えない、とは、決定的に違うことだ。
目が悪いなら、近くに行って目を近づけてみればわかる。でも、色覚の相違は、いくら近くで見ても解決しない。
色覚の問題と、視力の問題は全く異なるのだ。
「形」の問題なら、目を近づければ、絶対にどこかで整合する。最悪、手で触れば確認できる。人と人は、その共通認識から対話を進めていけばいいのだ。
(これって、「どんなに意見が違う二人でも、話し合っていけば絶対に意見の一致する部分がある」、という話に似てる。)
ところが、色覚の場合は、目を近づけようとどうしようと、わからないものはわからない。色についての感覚が違う人同士が、対話を重ねて解決することではないのだ。
(上の例になぞらえて言えば、「意見が違う二人は、絶対に一致しあうことがない。なぜなら、認識のいちばん根本は、決してわかりあえないから。」ということになる。)
多数派の、普通の色覚を持った人からみれば、色弱の人はエイリアンに思えるかもしれない。だって、自分と同じ世界を見てると思っていると、根本のところで見え方が違うのだから。
さて。
で、そういう、「絶対的な他者」を経験できるショックな一瞬って、日常生活の中では、色ぐらいしかないのではないだろうか。
隣り合っている誰かさんは、自分と違う世界を見ている、らしい。そして、それを確かめる方法はない。相手の頭の中に入りでもしない限り。
、、、、、、、
とまあ、そういうことを踏まえて「色」にまつわる展覧会を見ていると、そのへんについて、ちょっとちょっかいを出してみたくなったのである。
すごく哲学的な話のふりして、実はすごく現実的な話でもあるのだけれど、要するに、「人はがんばれば分かり合える」ということを、色覚は根本的に否定しているのだ。
うーん、今日はちょっと恐い話になってしまったか。
でも、私は、「だから人は分かり合えないんだ」、なんて絶望的なことを言いたいんではない。
むしろ、絶対に分かり合えないはずの人同士が、同じものを見て感動したり、恋に落ちたり、、、、、同じコトを感じることがあるのってすごい、ということを言いたいのだ。
そして、それに気づくという意味では、色弱の人がいるっていいことじゃん、とも思う。
だけれども、まあ、長くなるので、この話はずっと未来のいつかに、またきちんと。
平野先生の記事を読むにつけ。
色覚の問題って、とても面白いと思っているので、今日はその話をしてみよう。
色って、かなり特殊な存在だと思うのだ。相互認識において。
たとえば、色弱の人に、一般的な色覚の人が出会ったと考えてみて欲しい。
私には苦もなく区別がつく色が、彼には区別がつかない。
おんなじ色に見える、ようだ。
じゃあ、「彼にはなぜこんなに違う二つの色が、おんなじに見えるんだろう」。
でも一方で、色弱のひとはこう思っているかもしれない。
「僕には同じに見える一つの色が、彼にはなんで違って見えるんだろう」。
これは、視力が弱くてよく見えない、とは、決定的に違うことだ。
目が悪いなら、近くに行って目を近づけてみればわかる。でも、色覚の相違は、いくら近くで見ても解決しない。
色覚の問題と、視力の問題は全く異なるのだ。
「形」の問題なら、目を近づければ、絶対にどこかで整合する。最悪、手で触れば確認できる。人と人は、その共通認識から対話を進めていけばいいのだ。
(これって、「どんなに意見が違う二人でも、話し合っていけば絶対に意見の一致する部分がある」、という話に似てる。)
ところが、色覚の場合は、目を近づけようとどうしようと、わからないものはわからない。色についての感覚が違う人同士が、対話を重ねて解決することではないのだ。
(上の例になぞらえて言えば、「意見が違う二人は、絶対に一致しあうことがない。なぜなら、認識のいちばん根本は、決してわかりあえないから。」ということになる。)
多数派の、普通の色覚を持った人からみれば、色弱の人はエイリアンに思えるかもしれない。だって、自分と同じ世界を見てると思っていると、根本のところで見え方が違うのだから。
さて。
で、そういう、「絶対的な他者」を経験できるショックな一瞬って、日常生活の中では、色ぐらいしかないのではないだろうか。
隣り合っている誰かさんは、自分と違う世界を見ている、らしい。そして、それを確かめる方法はない。相手の頭の中に入りでもしない限り。
、、、、、、、
とまあ、そういうことを踏まえて「色」にまつわる展覧会を見ていると、そのへんについて、ちょっとちょっかいを出してみたくなったのである。
すごく哲学的な話のふりして、実はすごく現実的な話でもあるのだけれど、要するに、「人はがんばれば分かり合える」ということを、色覚は根本的に否定しているのだ。
うーん、今日はちょっと恐い話になってしまったか。
でも、私は、「だから人は分かり合えないんだ」、なんて絶望的なことを言いたいんではない。
むしろ、絶対に分かり合えないはずの人同士が、同じものを見て感動したり、恋に落ちたり、、、、、同じコトを感じることがあるのってすごい、ということを言いたいのだ。
そして、それに気づくという意味では、色弱の人がいるっていいことじゃん、とも思う。
だけれども、まあ、長くなるので、この話はずっと未来のいつかに、またきちんと。
2009年07月27日
連歌なアート
まだしつこく、スノドカフェ『アートと学びの企画』での議論について考えている。頭から離れなかったのは、静岡でなんでアート?ということについてだ。
「なぜ静岡」という問いは厄介だ。
すごい人はいる。東京に。NYに。ロンドンに。
でも、そうだとしたら、静岡でアートを語る積極的な意味ってあるんだろうか。
でも、先日の議論と、それを受けた平野さんの『脳内探訪』「キャッチフレーズを入れたくなると云った理由(※きっとまだ二三筆を入れるだろう)」を読んでいたら、なんだか少し見えてきたことがある。
平野さんは、古池さんの作品について、「キャッチフレーズを入れたいと思った」という。
写真だけでは成立していないから、言葉を足そう、という発想ではない。そこは平野さん、むしろ逆なのだ。
「それはむしろ、写真単独、あるいは「シャッター以前」にビジュアル・メッセージが完成されている場合におきる。それは完成してしまったものを敢えてもう一度解体したくなる行為である。」(上記『脳内探訪』より引用)
作者とは別の「他者」が言葉を足して新たな作品が生まれてしまうこと。
ここに、「静岡でやるアート」へのヒントがあるような気がしたのだ。
たとえば「連歌」という補助線を引いてみる。
連歌は、ある言葉に、みんなが順番に、新たな言葉を足していく。新しいイメージを付け加えていくことがルールとして定められているので、常にイメージの跳躍がある。ここで大事なのは、この跳躍が次々と別の参加者によって行われることだ。個人で仕組んだ跳躍ではなく、逆に、個人では思ってもいなかった意味が他者によって足されることが繰り返されて、総体としては誰もコントロールできない一つの作品が生まれていく。
作者も鑑賞者も混然一体となったイメージのスパーク。
先日、私は「アートの地産地消」などという舌足らずな表現をしてしまったが、もっと正確に言えば、「アーティストの顔が見えるアート」。(どうしても農産物の比喩になってしまうが、、、、(笑))
既に完成している作品を一つの素材として、また新たな作品を作ってしまう行為、これは試みる価値のあることのような気がしたのだ。
「なぜ静岡」という問いは厄介だ。
すごい人はいる。東京に。NYに。ロンドンに。
でも、そうだとしたら、静岡でアートを語る積極的な意味ってあるんだろうか。
でも、先日の議論と、それを受けた平野さんの『脳内探訪』「キャッチフレーズを入れたくなると云った理由(※きっとまだ二三筆を入れるだろう)」を読んでいたら、なんだか少し見えてきたことがある。
平野さんは、古池さんの作品について、「キャッチフレーズを入れたいと思った」という。
写真だけでは成立していないから、言葉を足そう、という発想ではない。そこは平野さん、むしろ逆なのだ。
「それはむしろ、写真単独、あるいは「シャッター以前」にビジュアル・メッセージが完成されている場合におきる。それは完成してしまったものを敢えてもう一度解体したくなる行為である。」(上記『脳内探訪』より引用)
作者とは別の「他者」が言葉を足して新たな作品が生まれてしまうこと。
ここに、「静岡でやるアート」へのヒントがあるような気がしたのだ。
たとえば「連歌」という補助線を引いてみる。
連歌は、ある言葉に、みんなが順番に、新たな言葉を足していく。新しいイメージを付け加えていくことがルールとして定められているので、常にイメージの跳躍がある。ここで大事なのは、この跳躍が次々と別の参加者によって行われることだ。個人で仕組んだ跳躍ではなく、逆に、個人では思ってもいなかった意味が他者によって足されることが繰り返されて、総体としては誰もコントロールできない一つの作品が生まれていく。
作者も鑑賞者も混然一体となったイメージのスパーク。
先日、私は「アートの地産地消」などという舌足らずな表現をしてしまったが、もっと正確に言えば、「アーティストの顔が見えるアート」。(どうしても農産物の比喩になってしまうが、、、、(笑))
既に完成している作品を一つの素材として、また新たな作品を作ってしまう行為、これは試みる価値のあることのような気がしたのだ。
2009年07月26日
棒。棒。棒。
5歳になったもらっちゃ王。
彼は棒が大好き。どこかで棒があると、必ず持ち帰る。だから、どんどん棒が増えていく。

そういえば、自分も子供の頃は棒を持つのが好きだったな。

普段自分の手が届かないところに、しかも違う質感で触れられる不思議。
なんかちょっと、自分が外部に延長した気がして、万能感みたいなものも感じた。
もらっちゃ王にとって、棒は、世界と触る触角、なのかもしれない。
彼は棒が大好き。どこかで棒があると、必ず持ち帰る。だから、どんどん棒が増えていく。

そういえば、自分も子供の頃は棒を持つのが好きだったな。

普段自分の手が届かないところに、しかも違う質感で触れられる不思議。
なんかちょっと、自分が外部に延長した気がして、万能感みたいなものも感じた。
もらっちゃ王にとって、棒は、世界と触る触角、なのかもしれない。
タグ :殿姫もらっちゃ王
Posted by しぞーか式。 at
23:31
│Comments(0)
2009年07月25日
恐竜、ガブリ‼

 もらっちゃ王、5歳になった。
もらっちゃ王、5歳になった。プレゼントを探しに『トイザらス』へ。
「俺を買ってくれよ〜」
いいじゃん恐竜、ってことで父も賛成。1980円だったし。
しかし、結局心変わりして『侍戦隊ダイカイオー』に。
父は若干不満である。
が、もらっちゃ王は御満悦の様子。
なぜか「ダイカイオー」を布団に寝かせたりご飯をあげたり、、、、おままごとをしていた。
「落ち着いて食べなさい」
それって……
もらっちゃ王がいつも言われていることであった。
そういえば。安倍川の花火大会、8日に延期になったという噂がある。
1日は清水港祭りがあるので、「静岡市の花火大会」を同時開催できないというリクツ。
正式発表が待ち遠しい。
2009年07月24日
送別会にて
先日送別会があった。
東京に去年転勤した同僚がいる。彼が、今年東京に転勤する後輩たちに向けて、贈る言葉をファックスしていた。
会ではその代読があった。その中の言葉。
相手を精神的に追い詰めて撮影して、「がんばって追い込んだから、すごいシーンが撮れたね、よかったよかった」とか言っている人がいます。でも、そうやって相手を追い詰めて追い詰めるのがわれわれの本当の仕事なら、この会社に未来はないと思います。
しんどい誰かに寄り添って、一緒に苦しんでいるうちになにかが見えてくる、という仕事でなければ、この仕事はつまらないです。
そうなんだよね。
お酒を飲みながら、ちょっと心が震えた。
東京に去年転勤した同僚がいる。彼が、今年東京に転勤する後輩たちに向けて、贈る言葉をファックスしていた。
会ではその代読があった。その中の言葉。
相手を精神的に追い詰めて撮影して、「がんばって追い込んだから、すごいシーンが撮れたね、よかったよかった」とか言っている人がいます。でも、そうやって相手を追い詰めて追い詰めるのがわれわれの本当の仕事なら、この会社に未来はないと思います。
しんどい誰かに寄り添って、一緒に苦しんでいるうちになにかが見えてくる、という仕事でなければ、この仕事はつまらないです。
そうなんだよね。
お酒を飲みながら、ちょっと心が震えた。
タグ :送別会
2009年07月23日
2009年07月22日
おもいあふれて。
たとえば、新蒲原駅そばの、こんな楽園。
駅を出たら、もう入り口が見えている。

夕方4時からオープンという、すばらしい営業時間。

メニューには「落花生」、とだけあったけど、たぶん「ゆで落花生」だろうと思ったら案の定。
でもこのボリュームとは。

常連さんは、黙って座れば、、、、、で。
ほぼみなさんが、「焼酎『おーいお茶』割り」。
私は、なんとなく遠慮もあって瓶ビールを頼む。
黙ってキリンラガーが出てくる。
渋い選択。
(スーパードライを飲んでいた方もいたので、頼めば何でもあるんだろうけど。)
写真でわかるかな?
コップの下のほうが、ちょっとだけ波のようにデザインされているのが渋い。
しかも、大瓶390円なり。
安っ。
隣に岩科酒店があり、ここがやっている、という体なので、安くしているんだろうか。
それにしても。。。。。いい店だ。
常連さんも、実に心地よさそうにくつろいでいる。
みなさん、テレビに時々突っ込みを入れたりして、まったりしたいい感じになってきた。
そして、いつものことだけど、平日の早い時間なのに、結構満席に近い。
私はこの日は早朝から仕事だったので疲れていたせいか、よくお酒が回った。
明るいうちのお酒、至福です。

うみつぼ。うまい。

メニューがあふれて、壁にまで。
漢(おとこ)だね。
ごらんのとおり、ほとんどのメニューは200~300円。これも、安っ。
そして、さりげなく驚いたのが、清水の銘酒の『臥龍梅』大吟醸が置いてあること。
壁にグラス600円という張り紙があって、ほう、と。
ここの蔵、気に入った酒屋さんにしか卸さないので、置いてある店は限られている。
しかも、他の銘柄もなく、吟醸もなく、大吟醸だけとは、、、、。
これまた男らしい。
日本酒好きにはかなりツボなのでは。
なぜ臥龍梅?と伺ったら、古くからのつきあいだから、だって。
確かに、日めくりカレンダーも臥龍梅。
地域密着型、信じられるお店、という感じ。
ごちそうさまでした。
岩科酒場 16時~22時ごろ
日曜定休
駅を出たら、もう入り口が見えている。

夕方4時からオープンという、すばらしい営業時間。

メニューには「落花生」、とだけあったけど、たぶん「ゆで落花生」だろうと思ったら案の定。
でもこのボリュームとは。

常連さんは、黙って座れば、、、、、で。
ほぼみなさんが、「焼酎『おーいお茶』割り」。
私は、なんとなく遠慮もあって瓶ビールを頼む。
黙ってキリンラガーが出てくる。
渋い選択。
(スーパードライを飲んでいた方もいたので、頼めば何でもあるんだろうけど。)
写真でわかるかな?
コップの下のほうが、ちょっとだけ波のようにデザインされているのが渋い。
しかも、大瓶390円なり。
安っ。
隣に岩科酒店があり、ここがやっている、という体なので、安くしているんだろうか。
それにしても。。。。。いい店だ。
常連さんも、実に心地よさそうにくつろいでいる。
みなさん、テレビに時々突っ込みを入れたりして、まったりしたいい感じになってきた。
そして、いつものことだけど、平日の早い時間なのに、結構満席に近い。
私はこの日は早朝から仕事だったので疲れていたせいか、よくお酒が回った。
明るいうちのお酒、至福です。

うみつぼ。うまい。

メニューがあふれて、壁にまで。
漢(おとこ)だね。
ごらんのとおり、ほとんどのメニューは200~300円。これも、安っ。
そして、さりげなく驚いたのが、清水の銘酒の『臥龍梅』大吟醸が置いてあること。
壁にグラス600円という張り紙があって、ほう、と。
ここの蔵、気に入った酒屋さんにしか卸さないので、置いてある店は限られている。
しかも、他の銘柄もなく、吟醸もなく、大吟醸だけとは、、、、。
これまた男らしい。
日本酒好きにはかなりツボなのでは。
なぜ臥龍梅?と伺ったら、古くからのつきあいだから、だって。
確かに、日めくりカレンダーも臥龍梅。
地域密着型、信じられるお店、という感じ。
ごちそうさまでした。
岩科酒場 16時~22時ごろ
日曜定休
2009年07月21日
静かなる大掃除。
この10日ばかり、時間があるとiTunesの音楽にジャケット写真を読み込ませている。

iTunesは、ある程度自動的にジャケット写真をダウンロードしてくれる。しかし、それはあくまで「ある程度」。マニアックな音源だと、まったく引っかからないので、上の写真のごとく、「♪」のついている四角が並ぶことになる。
だんだんアルバムの枚数が増えてくると、これはかなり不便。人間は文字情報だけだと、膨大な情報は管理できないのだ。そういうわけで、今まではいちいちアーティスト名やアルバム名を読んで探して、それでも、タイトルだけだと、このアルバムって何だっけ、誰が参加していたんだっけ、なぜ買ったんだっけ、、、、?と、自分の行動ながら、思い出せなくなってきたのだ。
私は映像で記憶するタイプの人間ということもあるので、ここは一念発起して、ウエブからアルバム写真をあつめて入れ込んでみている。

自分の処理速度が早くなった感じ。それぞれのアルバムの自分なりの位置づけがすぐにわかって、ちょっと自分が頭が良くなったような錯覚すら、、、、、。
かなり快感である。
とはいえ、まだ道なかば。
初日は、半日もかけてアルファベットのCまでしかいかず、泣きそうになった。
まあ、ぼちぼちやっていきます。

iTunesは、ある程度自動的にジャケット写真をダウンロードしてくれる。しかし、それはあくまで「ある程度」。マニアックな音源だと、まったく引っかからないので、上の写真のごとく、「♪」のついている四角が並ぶことになる。
だんだんアルバムの枚数が増えてくると、これはかなり不便。人間は文字情報だけだと、膨大な情報は管理できないのだ。そういうわけで、今まではいちいちアーティスト名やアルバム名を読んで探して、それでも、タイトルだけだと、このアルバムって何だっけ、誰が参加していたんだっけ、なぜ買ったんだっけ、、、、?と、自分の行動ながら、思い出せなくなってきたのだ。
私は映像で記憶するタイプの人間ということもあるので、ここは一念発起して、ウエブからアルバム写真をあつめて入れ込んでみている。

自分の処理速度が早くなった感じ。それぞれのアルバムの自分なりの位置づけがすぐにわかって、ちょっと自分が頭が良くなったような錯覚すら、、、、、。
かなり快感である。
とはいえ、まだ道なかば。
初日は、半日もかけてアルファベットのCまでしかいかず、泣きそうになった。
まあ、ぼちぼちやっていきます。
タグ :iTunes
2009年07月20日
当りっ!!!

今日は自宅で、ししとうの焼いたのと日本酒。
・・・・・・・・美味い。
食べていたら、姫(小3女子)が欲しそうだったので、辛いのあるからアタリに気をつけてね、と言った。
そしたら、「辛いのってアタリなの?ハズレなの?」と聞かれた。
それは人によるよね。
なんて言いながら飲むお酒は絶妙に美味也。
2009年07月19日
どんどん食べる。
あっついですね。
というわけで、脊髄反射的にウナギネタ。

庶民派鰻の代表、『水泉園』。
三島生まれの知り合いに、おいしいよ、と聞いて行って大感激。
三島は、湧き水が豊かな町。養殖した鰻を、三島の水に漬けておくだけで臭みが消え、おいしい鰻になるという。『桜家』なんかは、まさにそれが売り。そして、カンバンにたがわないおいしい鰻を出す。ってなわけで、三島にはおいしい鰻屋さんは数多いんだけど、あえてお勧めするのはこちら。

この『水泉園』のタレは、レモンを多めに入れてあって、かなり酸味が強い。
たぶん、鰻を食べ慣れている人ほど、ドキッとする味。知り合いのある人は、はっきり、あそこはダメだよ、と言っている。
でもね。
戦後間もなくお店を立ち上げて、(たぶんたくさんの老舗があるなかで)おいしい鰻を模索して、そうしてたどりついたのが、キレのある酸味だった、という歴史に、私なんかはちょっとキュンとしてしまうのだ。もともと鰻って、基本的には「薬膳」みたいなもんで、(誤解を恐れずにいえば)そんなに日常的に食べるものではない。村松ともみさんなんかは、桜家を評して、「味覚と一緒に、腹もたれするぐらい食べたという満腹感が大事」と言っているぐらいで、要するに非日常の食べ物だったのだ。
そういう文脈の中で、最後まで食べ飽きずに楽しんでもらう方策として、柑橘系の酸味を入れるというのが、なんか、私のツボなのだ。
まあ、そういうゴタクはおいておいて、暑い季節に、最後までおいしく食べて、もたれない感じを体験するのに、一度挑戦する価値はあると思う。ちなみに、うな重が2000円より。高級店よりは、かなり安いです。
『水泉園』 TEL 055-972-1097
住所 静岡県三島市一番町1-28
営業時間 11:00~19:00 水曜休み
というわけで、脊髄反射的にウナギネタ。

庶民派鰻の代表、『水泉園』。
三島生まれの知り合いに、おいしいよ、と聞いて行って大感激。
三島は、湧き水が豊かな町。養殖した鰻を、三島の水に漬けておくだけで臭みが消え、おいしい鰻になるという。『桜家』なんかは、まさにそれが売り。そして、カンバンにたがわないおいしい鰻を出す。ってなわけで、三島にはおいしい鰻屋さんは数多いんだけど、あえてお勧めするのはこちら。

この『水泉園』のタレは、レモンを多めに入れてあって、かなり酸味が強い。
たぶん、鰻を食べ慣れている人ほど、ドキッとする味。知り合いのある人は、はっきり、あそこはダメだよ、と言っている。
でもね。
戦後間もなくお店を立ち上げて、(たぶんたくさんの老舗があるなかで)おいしい鰻を模索して、そうしてたどりついたのが、キレのある酸味だった、という歴史に、私なんかはちょっとキュンとしてしまうのだ。もともと鰻って、基本的には「薬膳」みたいなもんで、(誤解を恐れずにいえば)そんなに日常的に食べるものではない。村松ともみさんなんかは、桜家を評して、「味覚と一緒に、腹もたれするぐらい食べたという満腹感が大事」と言っているぐらいで、要するに非日常の食べ物だったのだ。
そういう文脈の中で、最後まで食べ飽きずに楽しんでもらう方策として、柑橘系の酸味を入れるというのが、なんか、私のツボなのだ。
まあ、そういうゴタクはおいておいて、暑い季節に、最後までおいしく食べて、もたれない感じを体験するのに、一度挑戦する価値はあると思う。ちなみに、うな重が2000円より。高級店よりは、かなり安いです。
『水泉園』 TEL 055-972-1097
住所 静岡県三島市一番町1-28
営業時間 11:00~19:00 水曜休み
2009年07月18日
発表会

静岡大学のキャンパスで、「静岡の文化」の発表会に。

取材すること、の喜びにあふれた発表会。今後も楽しんで授業できるといいですね。大変だろうとは思うけど、こんなに役立つ授業はない、とも思う。
そして、、、


実は、この発表のちょっと前。
静岡大学にバスで向かおうとして、乗りすごして終点まで行ってしまっていた。
たまたま一緒に乗りあわせ、静大に向かうはずの某先生(都市がご専門)も一緒に困惑、、、、、
のはずが、終点で古い土蔵を発見し、大興奮!!!
転んでもタダではおきない、というより、むしろ転んで喜んでる感じが、、、、、。
こういう先生だから、勉強の楽しさをきちっと伝えられるんだろうなあ。
2009年07月17日
あかるいへやで、じーーーーーっ。(オルタナイーヴ3)
まだまだ続く、『アートと学びの企画』の余波。
今日は古池大介さんの写真を見た感想について。
私は細部に目が行ってしまうタイプ。
以前子どもを連れて実家に帰省していたときのことだが、眠っている子どもの隣で横になっていたら、子どもの生え際辺りの髪の毛の流れかたが面白くて、つい夢中になって見ていた。そうしたら、親に、「お前は昔からそうやってじーっと見つめる子だった」と笑われた。
なんというか、細かいものをじっと見ているのが苦にならない、、、、というか、正直言うと大好きなのだ。
で、今回の古池さんの作品でわたしが「じーっと見た」ものたち。
海に舟が数隻浮かんでいる写真では、他の船は海の中でただ浮かんでいるのに、中の一隻だけ航跡がまっすぐに伸びているところ。この船だけ動いているんだろうか。スピードが違うんだろうか。その航跡を、じ~~~~っ。
海に飛び込もうとしている二人の少年の写真では、一方の子の膝小僧の擦り傷。そして、片足を手で持って、手と腕で三角形を作っている感じが気になる。こういう姿勢、よくした。ああ、夏休みな感じ。冷えた身体をタオルで拭くと、ほかほかしてきて凄く気持ちいいんだよなあ、、、、と、じーーーーーーっ。
ドアが並んでいる作品では、壁に残っているテープ痕みたいなのも気になったが、ドアに書いてあるルームナンバーのような看板の番号が102の隣が202であるところ。普通、マンションの部屋番号であれば、102の次は103だよな。でも、そういえば昔住んでいた会社の寮の倉庫は、102、202、302の順に並んでたな、なんて思い出しながら、じーーーーーーっ。
しかし。
気になる部分って、たいてい他人と共有できない。だから、kenaato先生が、ドアのナンバリングが気になっていたと言ってくれたときは結構嬉しかった。
私の鑑賞は、常にこういうディテールに入っちゃう感じである。
時に、「職業病ですね」「さすが日々の鍛錬が、、、」なんていわれるのだが、それは誤解。むしろ、ディテールにばっかりはまっていると、仕事にならないんです。仕事にはもっと俯瞰的な視点が必要なので、私が仕事を通して学んできたのは、むしろ、そういうディテールにマニアックにとらわれずに「みんなが見ているように見る」ことなのだ。
えーと、よそみちにそれてしまったが、とにかく、こういう「自分だけに響くディテール」を大事に大事にして、一冊の写真論をものした批評家がいる。
ロラン・バルト。
彼の『明るい部屋』という本は、徹底して、撮る人からではなく、見る人からの視点で描かれた写真論だ。バルトは、人が写真からだれもが共通して読み取れること(「この写真は黒人の家族を写したものだ」、「この写真は死刑囚を写したものだ」etc...)を「ストゥディウム」といい、それに対して、私だけがごくごく個人的に刺激を受ける部分を「プンクトゥム」と名づけた。
例えば、バルトは見知らぬ黒人の家族写真に妙に惹かれる。考えていくうちに、それは女性の首飾りが母が若い頃の写真で見につけていたものと似ていたからだ、という記憶にたどりつく。この首飾りが、彼のいう「プンクtゥム(突き刺すもの)」。他の人にはなんでもないディテールが、バルトにとってだけは、自分を刺し貫くものとなる。
『明るい部屋』は、彼の最晩年の本だという。しかも、それまでの彼の「怜悧で客観的な分析」というイメージは影をひそめ、ある時にはほとんどセンチメンタルな自伝のようになる。
世界を冷静に語り続けたバルトだが、ここで奇妙にも自分の子供時代の記憶を克明に語っているのは、「プンクトゥム」という概念が、そこまで自分を明かさないと伝わらないものだったからだろう。
さらに、バルトは、写真を「それは・かつて・あった」ものだという。処刑される前の若者の写真を見たバルトは、「それはかつてあった」という。(=「この若者はかつて存在していて、今はいない」)。
一枚の写真を見たとき、「それを撮った時点」(若者は死ぬべき運命にあり、それでも生きている、という瞬間)と、「今」(若者は死んでいる)という二つの時間を並行して感じ、驚くことが写真の本質なのだ、とバルトは言う。
そういう、取り返しのつかない時間の経過を突きつけられるというか、失われたものへの愛惜というか、、、、そんな感じは、確かに写真を見るといつも感じるものだった。
古池さんの写真からはなんとなく離れてしまったようで、実はあんまり離れていないのだけど。
私にとって写真を見るというのは、他のアートよりもずーっとーっと個人的な体験らしい。
こう書いていて思いついたことがある。
まだほんとにヒント、という程度の思いつきだが。バルトは、徹底的に見る側にたった写真論を書いたわけだが、実は撮影する人の側から見ても有効な理論という気がしてきた。
追記。
上記の「それは・かつて・あった」という感じは、CGの発達や、デジタル写真になって画像加工が簡単になったことで、成立が怪しくなっているのではないか。
というのは、「それは・かつて・あった」と思えるためには、撮影した写真が、ある瞬間の事実をそのまま写したというのが前提だからだ。でも、最近は、デジカメの発達もあって、写真が様々に加工されていることは、当然のことになってきた。(アイコラを見て「それは・かつて・あった」とは思いませんよね。コラージュって、そういう意味では写真ではなくて、絵だ。)そうなると、素朴に「それは・かつて・あった」という感慨を持つ世代は、私辺りで終わってしまうのかなあ、と思うのだ。
さらにどうでもいい追記。
昔風、というと「セピア色」を思い出したり、「青っぽい色彩」を思い出すのは、それぞれ白黒写真、カラー写真が古びた時のイメージと密接に結びついている。
でも、原理上古びないのがデジタル写真。では、これから、「古さを感じさせる映像」の定番は、どんなものになるのだろう。(デジタルのノイズがバリバリに乗った写真?まさか??)
なんだか、いつにも増してまとまりがない話になってしまったが、、、、。
バルトを読んだときは、「こういうふうに写真を見てもいいんだな」と、本当に救われた気がしたことを思いだしたりしつつ、おやすみなさい。
今日は古池大介さんの写真を見た感想について。
私は細部に目が行ってしまうタイプ。
以前子どもを連れて実家に帰省していたときのことだが、眠っている子どもの隣で横になっていたら、子どもの生え際辺りの髪の毛の流れかたが面白くて、つい夢中になって見ていた。そうしたら、親に、「お前は昔からそうやってじーっと見つめる子だった」と笑われた。
なんというか、細かいものをじっと見ているのが苦にならない、、、、というか、正直言うと大好きなのだ。
で、今回の古池さんの作品でわたしが「じーっと見た」ものたち。
海に舟が数隻浮かんでいる写真では、他の船は海の中でただ浮かんでいるのに、中の一隻だけ航跡がまっすぐに伸びているところ。この船だけ動いているんだろうか。スピードが違うんだろうか。その航跡を、じ~~~~っ。
海に飛び込もうとしている二人の少年の写真では、一方の子の膝小僧の擦り傷。そして、片足を手で持って、手と腕で三角形を作っている感じが気になる。こういう姿勢、よくした。ああ、夏休みな感じ。冷えた身体をタオルで拭くと、ほかほかしてきて凄く気持ちいいんだよなあ、、、、と、じーーーーーーっ。
ドアが並んでいる作品では、壁に残っているテープ痕みたいなのも気になったが、ドアに書いてあるルームナンバーのような看板の番号が102の隣が202であるところ。普通、マンションの部屋番号であれば、102の次は103だよな。でも、そういえば昔住んでいた会社の寮の倉庫は、102、202、302の順に並んでたな、なんて思い出しながら、じーーーーーーっ。
しかし。
気になる部分って、たいてい他人と共有できない。だから、kenaato先生が、ドアのナンバリングが気になっていたと言ってくれたときは結構嬉しかった。
私の鑑賞は、常にこういうディテールに入っちゃう感じである。
時に、「職業病ですね」「さすが日々の鍛錬が、、、」なんていわれるのだが、それは誤解。むしろ、ディテールにばっかりはまっていると、仕事にならないんです。仕事にはもっと俯瞰的な視点が必要なので、私が仕事を通して学んできたのは、むしろ、そういうディテールにマニアックにとらわれずに「みんなが見ているように見る」ことなのだ。
えーと、よそみちにそれてしまったが、とにかく、こういう「自分だけに響くディテール」を大事に大事にして、一冊の写真論をものした批評家がいる。
ロラン・バルト。
彼の『明るい部屋』という本は、徹底して、撮る人からではなく、見る人からの視点で描かれた写真論だ。バルトは、人が写真からだれもが共通して読み取れること(「この写真は黒人の家族を写したものだ」、「この写真は死刑囚を写したものだ」etc...)を「ストゥディウム」といい、それに対して、私だけがごくごく個人的に刺激を受ける部分を「プンクトゥム」と名づけた。
例えば、バルトは見知らぬ黒人の家族写真に妙に惹かれる。考えていくうちに、それは女性の首飾りが母が若い頃の写真で見につけていたものと似ていたからだ、という記憶にたどりつく。この首飾りが、彼のいう「プンクtゥム(突き刺すもの)」。他の人にはなんでもないディテールが、バルトにとってだけは、自分を刺し貫くものとなる。
『明るい部屋』は、彼の最晩年の本だという。しかも、それまでの彼の「怜悧で客観的な分析」というイメージは影をひそめ、ある時にはほとんどセンチメンタルな自伝のようになる。
世界を冷静に語り続けたバルトだが、ここで奇妙にも自分の子供時代の記憶を克明に語っているのは、「プンクトゥム」という概念が、そこまで自分を明かさないと伝わらないものだったからだろう。
さらに、バルトは、写真を「それは・かつて・あった」ものだという。処刑される前の若者の写真を見たバルトは、「それはかつてあった」という。(=「この若者はかつて存在していて、今はいない」)。
一枚の写真を見たとき、「それを撮った時点」(若者は死ぬべき運命にあり、それでも生きている、という瞬間)と、「今」(若者は死んでいる)という二つの時間を並行して感じ、驚くことが写真の本質なのだ、とバルトは言う。
そういう、取り返しのつかない時間の経過を突きつけられるというか、失われたものへの愛惜というか、、、、そんな感じは、確かに写真を見るといつも感じるものだった。
古池さんの写真からはなんとなく離れてしまったようで、実はあんまり離れていないのだけど。
私にとって写真を見るというのは、他のアートよりもずーっとーっと個人的な体験らしい。
こう書いていて思いついたことがある。
まだほんとにヒント、という程度の思いつきだが。バルトは、徹底的に見る側にたった写真論を書いたわけだが、実は撮影する人の側から見ても有効な理論という気がしてきた。
追記。
上記の「それは・かつて・あった」という感じは、CGの発達や、デジタル写真になって画像加工が簡単になったことで、成立が怪しくなっているのではないか。
というのは、「それは・かつて・あった」と思えるためには、撮影した写真が、ある瞬間の事実をそのまま写したというのが前提だからだ。でも、最近は、デジカメの発達もあって、写真が様々に加工されていることは、当然のことになってきた。(アイコラを見て「それは・かつて・あった」とは思いませんよね。コラージュって、そういう意味では写真ではなくて、絵だ。)そうなると、素朴に「それは・かつて・あった」という感慨を持つ世代は、私辺りで終わってしまうのかなあ、と思うのだ。
さらにどうでもいい追記。
昔風、というと「セピア色」を思い出したり、「青っぽい色彩」を思い出すのは、それぞれ白黒写真、カラー写真が古びた時のイメージと密接に結びついている。
でも、原理上古びないのがデジタル写真。では、これから、「古さを感じさせる映像」の定番は、どんなものになるのだろう。(デジタルのノイズがバリバリに乗った写真?まさか??)
なんだか、いつにも増してまとまりがない話になってしまったが、、、、。
バルトを読んだときは、「こういうふうに写真を見てもいいんだな」と、本当に救われた気がしたことを思いだしたりしつつ、おやすみなさい。
2009年07月16日
灯籠流し




家族で清水の灯籠流しに。
綺麗だった。
イラストは、まあ見ればわかることだが、右が姫(小3女子)、左がもらっちゃ王(4歳男子)。
左の絵の顔に縦線があるのは、ちびまる子ちゃんによく出てくる血の気が引いた時の顔、、、、、ではなくて、戦隊もののヒーロー。『ディケード』って言ってたかな。
2009年07月16日
2009年07月15日
メタ議論、メタメタ議論への補助線 (オルタナイーヴ2)
先週土曜、スノドカフェの『アートと学びの企画3』(講師:古池大介氏)に行ってきた。
なかなかに辛い会でした。
今日は、その辛さについて考えてみる。
合評の場は「なまもの」だし、ウッ、と言葉に詰まる瞬間もある。これまでの『アートと学びの企画』の中でも息苦しさを感じることは毎回あった。でも、今までは、考え詰めて行くうちになんとか思考の補助線が見えてきて、最後には、「話がつながった!」「切り抜けた‼」という達成感があったわけで。。。。。。
今回は出口を探しても探しても光が見えず。探るうちに論点だけが拡散していき、話は迷走したまま。後半、作品の感想をみんなが言って辛うじて会の体裁だけ整った、という感じだった。古池さんには申し訳なかったが、かなり困った会になってしまったと思う。
今までは話が混線してもそれが新たな話への呼び水になったりして、かえってスリリングだったんだけど、3回目にして本当の渾沌にあいまみえたという感じ。話していればなんとか結論は見えてくるさ、という慢心もあったなあ。唐突なたとえ話で恐縮だが、バーベキューで、みんなが、「何をすればいいんですか?」と困惑しつつ作業が止まっているような状態、アレだったように思う。
ふーむ。
会の副題でもある「セレンディピティ」にふさわしい補助線は、なかったのだろうか。
Wikkipediaによれば、「セレンディピティ」とは、
「何かを探している時に、探しているものとは別の価値あるものを見つける能力・才能を指す言葉である。何かを発見したという「現象」ではなく、何かを発見をする「能力」のことを指す。平たく云えば、ふとした偶然をきっかけに、幸運を掴むことである。」
なるほど、そういうことか。
そうだとすれば、このブログで、先日の『転校生』同窓会バージョンについて触れたときも、結局、セレンディピティについて書いていたんだな。
この時のブログの主旨をかいつまんでいえば、、、、
『転校生』の演出家、飴屋法水さんは、いつも偶然を呼び込み、作品にする事に成功している(=セレンディピティの能力が高い)。しかし、本人とお話してみると、単に幸運なだけではない。常に何かを発見をしようという「普段の・不断の」心構えをもって暮らし、幸運を見過ごさないのがセレンディピティなのではないか、と気付いた。
、、、、、、というようなお話。
さて、今回の『アートと学びの企画』でセレンディピティーが発揮できなかった(と個人的には感じている)のは、普段のアンテナの張り方が不十分で周りが見えず、本当はたくさんあった(であろう)幸運の種を芽吹かせる事ができなかった、ということが、一番反省すべき点ということになる。
まあ、まだよちよち歩きの会ということで、これをどうして行くかという前向きな方向にアタマを切り替えていこう。平野さんがウエブ「脳内探訪」の中で書いておられるように、新しい「議論の進め方」から探るべきという指摘はまさにその通りで、あの場にいた者の一人として、反省しきり。
ではどうするか。
みんなで、まずは、今日何を議論するかを議論するという手もある。逆に、今日の議題はコレ、ととりあえず決めて議論を始めるが、盛り上がったら話が変わってもOK,という手もある。先ほどのバーベキューのたとえで言うと、最初に何をするかが明確なら、アドリブ進行へも移行しやすいから。
……でも、本当は分かっているんだ、話の流れに耳を澄ませていなかったことが一番の反省点だって。
さて、次はあの混沌の原因をもう少し思い出してみたい。
みんなは何を議論したかったのだろうか?
試みに、みんなの頭の隅にあった「問題意識」を推測も交えて思い出してみると……
☆サイトスペシフィックアートという概念をめぐって
偶然の出会いをアートに呼び込む方法
歴史は現在から遡って作られる
アートに地域の人を巻き込むこと
☆古池さんの作品をめぐって
どこからが作品なのか、創作行為とは(平野さんのWEB参照)
バルトの「プンクトゥム」概念(これは後日書きます、長くなるので)
写真と他のアートとの決定的な違いとは
☆スノドという「場」をめぐって
静岡を元気にさせるためにアートが活用できないか
行政主導のアート、アートの産業化の弊害
静岡にいながらアートは可能か
☆アートとコンセプト
アートが本来持っている野蛮な力の復権(まことちゃんハウス)
コンセプトがわかると現代アートは楽しい
ざっと思い出しただけでも、こんなに様々な議論が、それぞれの接点がないまま「ねじれの位置」で交錯していたわけで、まあまとまらないのもむべなるかな、である。みんなの問題意識がバラバラだったということは確か。ゆえに、何を考えればいいかすらわからないまま宙ぶらりんになる。それは、参加者にとっては凄いストレスになってしまう。
振り返って考えると、どれについて議論することもありえたと思う。でも結局、『スノドカフェ』は何を話す「べき」場なのか、何についての答えを探る場なのか、が明確でないということなのかなあ。
会の立ち上げ当初は、なんとはなしに、「最先端のアートについて聞きたい、話したい」という漠然とした場だったのが、「でも、私たちが話している「いまここ」って静岡じゃん」というアタリマエのことに気づいた瞬間、議論の足場自体を問われ始めている、ということなのかもしれない。
ふりかえってあの日、どんな議論をしたかったか、ということでいうと、古池さんの作品についての議論だったりする。koneeta先生も、ブログ『コニタス』でのリポートの後半でちらりと触れておられるが、、、、
作品を見ると、どうしても作者というモノガタリを見てしまう。作品の意味や、作者のことを考えてしまうのだ。
個人的には、次の大きな宿題となることが見えてきた、重要な会だった第3回『アートと学び』。このへんは、スノドの主のご意見も聞いてみたいと思う。20日、スノドへいけるといいけど、、、、。
なかなかに辛い会でした。
今日は、その辛さについて考えてみる。
合評の場は「なまもの」だし、ウッ、と言葉に詰まる瞬間もある。これまでの『アートと学びの企画』の中でも息苦しさを感じることは毎回あった。でも、今までは、考え詰めて行くうちになんとか思考の補助線が見えてきて、最後には、「話がつながった!」「切り抜けた‼」という達成感があったわけで。。。。。。
今回は出口を探しても探しても光が見えず。探るうちに論点だけが拡散していき、話は迷走したまま。後半、作品の感想をみんなが言って辛うじて会の体裁だけ整った、という感じだった。古池さんには申し訳なかったが、かなり困った会になってしまったと思う。
今までは話が混線してもそれが新たな話への呼び水になったりして、かえってスリリングだったんだけど、3回目にして本当の渾沌にあいまみえたという感じ。話していればなんとか結論は見えてくるさ、という慢心もあったなあ。唐突なたとえ話で恐縮だが、バーベキューで、みんなが、「何をすればいいんですか?」と困惑しつつ作業が止まっているような状態、アレだったように思う。
ふーむ。
会の副題でもある「セレンディピティ」にふさわしい補助線は、なかったのだろうか。
Wikkipediaによれば、「セレンディピティ」とは、
「何かを探している時に、探しているものとは別の価値あるものを見つける能力・才能を指す言葉である。何かを発見したという「現象」ではなく、何かを発見をする「能力」のことを指す。平たく云えば、ふとした偶然をきっかけに、幸運を掴むことである。」
なるほど、そういうことか。
そうだとすれば、このブログで、先日の『転校生』同窓会バージョンについて触れたときも、結局、セレンディピティについて書いていたんだな。
この時のブログの主旨をかいつまんでいえば、、、、
『転校生』の演出家、飴屋法水さんは、いつも偶然を呼び込み、作品にする事に成功している(=セレンディピティの能力が高い)。しかし、本人とお話してみると、単に幸運なだけではない。常に何かを発見をしようという「普段の・不断の」心構えをもって暮らし、幸運を見過ごさないのがセレンディピティなのではないか、と気付いた。
、、、、、、というようなお話。
さて、今回の『アートと学びの企画』でセレンディピティーが発揮できなかった(と個人的には感じている)のは、普段のアンテナの張り方が不十分で周りが見えず、本当はたくさんあった(であろう)幸運の種を芽吹かせる事ができなかった、ということが、一番反省すべき点ということになる。
まあ、まだよちよち歩きの会ということで、これをどうして行くかという前向きな方向にアタマを切り替えていこう。平野さんがウエブ「脳内探訪」の中で書いておられるように、新しい「議論の進め方」から探るべきという指摘はまさにその通りで、あの場にいた者の一人として、反省しきり。
ではどうするか。
みんなで、まずは、今日何を議論するかを議論するという手もある。逆に、今日の議題はコレ、ととりあえず決めて議論を始めるが、盛り上がったら話が変わってもOK,という手もある。先ほどのバーベキューのたとえで言うと、最初に何をするかが明確なら、アドリブ進行へも移行しやすいから。
……でも、本当は分かっているんだ、話の流れに耳を澄ませていなかったことが一番の反省点だって。
さて、次はあの混沌の原因をもう少し思い出してみたい。
みんなは何を議論したかったのだろうか?
試みに、みんなの頭の隅にあった「問題意識」を推測も交えて思い出してみると……
☆サイトスペシフィックアートという概念をめぐって
偶然の出会いをアートに呼び込む方法
歴史は現在から遡って作られる
アートに地域の人を巻き込むこと
☆古池さんの作品をめぐって
どこからが作品なのか、創作行為とは(平野さんのWEB参照)
バルトの「プンクトゥム」概念(これは後日書きます、長くなるので)
写真と他のアートとの決定的な違いとは
☆スノドという「場」をめぐって
静岡を元気にさせるためにアートが活用できないか
行政主導のアート、アートの産業化の弊害
静岡にいながらアートは可能か
☆アートとコンセプト
アートが本来持っている野蛮な力の復権(まことちゃんハウス)
コンセプトがわかると現代アートは楽しい
ざっと思い出しただけでも、こんなに様々な議論が、それぞれの接点がないまま「ねじれの位置」で交錯していたわけで、まあまとまらないのもむべなるかな、である。みんなの問題意識がバラバラだったということは確か。ゆえに、何を考えればいいかすらわからないまま宙ぶらりんになる。それは、参加者にとっては凄いストレスになってしまう。
振り返って考えると、どれについて議論することもありえたと思う。でも結局、『スノドカフェ』は何を話す「べき」場なのか、何についての答えを探る場なのか、が明確でないということなのかなあ。
会の立ち上げ当初は、なんとはなしに、「最先端のアートについて聞きたい、話したい」という漠然とした場だったのが、「でも、私たちが話している「いまここ」って静岡じゃん」というアタリマエのことに気づいた瞬間、議論の足場自体を問われ始めている、ということなのかもしれない。
ふりかえってあの日、どんな議論をしたかったか、ということでいうと、古池さんの作品についての議論だったりする。koneeta先生も、ブログ『コニタス』でのリポートの後半でちらりと触れておられるが、、、、
作品を見ると、どうしても作者というモノガタリを見てしまう。作品の意味や、作者のことを考えてしまうのだ。
個人的には、次の大きな宿題となることが見えてきた、重要な会だった第3回『アートと学び』。このへんは、スノドの主のご意見も聞いてみたいと思う。20日、スノドへいけるといいけど、、、、。
2009年07月14日
ポロポロ

上が3年前のiPodについていたイヤフォン。
下が先日買ったiPhoneについていたイヤフォン。
どうも新しい方はポロポロ耳から落ちると思っていたら、サイズが1
ミリほど小さくなっていた。
というわけで、未だに昔のイヤフォン愛用中。
ちなみにうちのもらっちゃ王(4歳男子)は何度聞いても
「iPhone」が覚えられず、イヤフォンと言って平気。
覚えない癖をつけると大人になってから苦労するよ。と、苦労している父
より助言。


 名前のない店。
名前のない店。