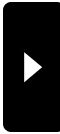2010年08月31日
2010年08月30日
イルカとジャンプ!
先日、小学校のころ、初めて自分でいいと思った音楽が矢野顕子だったという話をした。
これはこれで全く嘘偽りはないものの、この機会に自分的には誰にも話さずにおいていた話を書いてみる。
たぶん誕生日。おばあちゃんにお金を貰って、生まれて初めて自分の好きなレコード、
それもLPを買うことになった。当時の二千五百円は、かなり大金である。
でも、矢野顕子の声に憧れていた私は、迷わず矢野顕子のレコードを掴んで、…結局棚に戻してしまった。
それが、『いろはにこんぺいとう』。
中学生には、ちょっくら刺激が過ぎるビジュアルだった、のか、結局最初に買ったのは甲斐バンドだかオフコースだかになってしまった。

ああ、あそこで日和らなければ、みんなに胸を張れる音楽人生だったのに。いやいや、甲斐バンド、オフコースの音楽性云々ではなく、イルカとジャンプスーツのジャケットごときで日和った自分が残念でならなくて……。
これはこれで全く嘘偽りはないものの、この機会に自分的には誰にも話さずにおいていた話を書いてみる。
たぶん誕生日。おばあちゃんにお金を貰って、生まれて初めて自分の好きなレコード、
それもLPを買うことになった。当時の二千五百円は、かなり大金である。
でも、矢野顕子の声に憧れていた私は、迷わず矢野顕子のレコードを掴んで、…結局棚に戻してしまった。
それが、『いろはにこんぺいとう』。
中学生には、ちょっくら刺激が過ぎるビジュアルだった、のか、結局最初に買ったのは甲斐バンドだかオフコースだかになってしまった。

ああ、あそこで日和らなければ、みんなに胸を張れる音楽人生だったのに。いやいや、甲斐バンド、オフコースの音楽性云々ではなく、イルカとジャンプスーツのジャケットごときで日和った自分が残念でならなくて……。
2010年08月29日
回る王
今日は夏休み最後ということで、もらっちゃ王(6歳男子)と殿(高1女子。殿だけど女子)と、プールに行ってきた。案の定、もらっちゃ王の元気さに私も殿も降参だった。
もらっちゃ王はこの夏休みに水泳を習ってきたので、全然水は怖くない。でも、そうやって習った泳ぎを披露するでもなく、流れるプールで体をひたすらくるくる、時計回りに回りながら流されている。
くるくる回るのって、方向感覚がわからなくなる「めまい」遊びの一種。
その調子で、人生にも飛び込んだり巻き込まれたりして、
しかもそれを楽しんでほしいものである。
もらっちゃ王はこの夏休みに水泳を習ってきたので、全然水は怖くない。でも、そうやって習った泳ぎを披露するでもなく、流れるプールで体をひたすらくるくる、時計回りに回りながら流されている。
くるくる回るのって、方向感覚がわからなくなる「めまい」遊びの一種。
その調子で、人生にも飛び込んだり巻き込まれたりして、
しかもそれを楽しんでほしいものである。
Posted by しぞーか式。 at
23:13
│Comments(0)
2010年08月28日
ちょいとブラジルへ。


浜松駅前のブラジル料理店、兼ブラジルスーパー、
セルヴィツー。
久しぶりに行ったら一皿千円食べ放題になっていた。(昔は量り売りだった)
肉食のイメージが強いブラジル料理だけど、実は野菜も豊富。しかし、日系移民が来るまではこれほど野菜を食べなかったらしい。日系の移民が野菜作りも、野菜を食べる習慣も持ち込んだのだそうだ。
写真のごとく、味噌汁があったり、その名もズバリ、ニモノ、という醤油ベースの煮物もあるのだが、日本料理と違うのは砂糖を入れないこと。ブラジルの人は甘い料理は苦手らしいのだ。お菓子は逆に甘いのが大好きだけど。
さて、バイキング。
野菜料理もまあまああったのだけど、つい肉を沢山とってしまうのが我ながら貧乏なり。
見たこともない料理もあるけれど、お店の人に聞きながら(日本語は大体通じる)色々挑戦してみると楽しいと思う。
追伸。
この日は夜に行ったせいか、若干料理がすくなかったような。
もしかしたらランチのほうがいいかも。
お店情報はあとで補完します…
2010年08月27日
ほがみすーだないよ。
さらに続く、出雲弁シリーズ。
まずは、「ほがみ」。「ほが」は、たぶん「外(ほか)」かなあ。ともかく、「ほがみ」で「余所見」の意味になる。
「すー」は「する」の音便。「だないよ」は「じゃないよ」ということで、要するに「余所見をするんじゃないよ」という意味になる。
さて。
言葉を思い出すことは、その言葉を話していた時の自分を、時空を超えて思い出すこと、のような気がする。
いい例えなのかどうかはわからないけど、あるCDを、バスの中で初めて聞いたとして、そのCDを久しぶりに聞くと、ありありとどの路線に乗って、ぎらぎらの日差しの中で聞いていたことをありありと思い出すことがある。
ほんとうに瑣末なことを、とてもリアルに思い出すのだ。
「ほがみすーだないよ」には、小学校も低学年の頃、学校が終わっておばあちゃんの部屋に行ってお茶を飲んだ、その時のカルビーのかっぱえびせんが入っていた器(あとで聞いたら結構いいものだったらしい)とか、茶托に乗ったちいさな煎茶茶碗を思い出す。
お菓子を食べながら、よっぽどよそ見をしていたのだろうか。
まずは、「ほがみ」。「ほが」は、たぶん「外(ほか)」かなあ。ともかく、「ほがみ」で「余所見」の意味になる。
「すー」は「する」の音便。「だないよ」は「じゃないよ」ということで、要するに「余所見をするんじゃないよ」という意味になる。
さて。
言葉を思い出すことは、その言葉を話していた時の自分を、時空を超えて思い出すこと、のような気がする。
いい例えなのかどうかはわからないけど、あるCDを、バスの中で初めて聞いたとして、そのCDを久しぶりに聞くと、ありありとどの路線に乗って、ぎらぎらの日差しの中で聞いていたことをありありと思い出すことがある。
ほんとうに瑣末なことを、とてもリアルに思い出すのだ。
「ほがみすーだないよ」には、小学校も低学年の頃、学校が終わっておばあちゃんの部屋に行ってお茶を飲んだ、その時のカルビーのかっぱえびせんが入っていた器(あとで聞いたら結構いいものだったらしい)とか、茶托に乗ったちいさな煎茶茶碗を思い出す。
お菓子を食べながら、よっぽどよそ見をしていたのだろうか。
Posted by しぞーか式。 at
23:59
│Comments(0)
2010年08月26日
じきいないよ
ブログを書いてる時間がない時の出雲弁シリーズ。
「じきいないよ」ってわかりますか?
「じきに」は「直に」=「すぐに」。
「いない」は、出雲弁「いぬ=去ぬ」=帰るの尊敬語。
「よ」は調子を整えるための呼びかけかな?
要するに、「すぐにお帰りになりますよ」だ。我々出雲弁ネイティブは、こういうほとんど別言語の言い回しを、相手次第で標準語と使い分けて話せるわけだ。
そこへいくと、静岡弁は、標準語と近すぎるぶん、使い分けが難しいのだろう。「市役所」とか、「いや」とか、どっちも静岡風にアクセントを頭に置く人がいかに多いことか。
ところで、出雲に行ってきた殿(高1女子。殿だけど女子)、本日無事ご帰還。
おかえり〜。
「じきいないよ」ってわかりますか?
「じきに」は「直に」=「すぐに」。
「いない」は、出雲弁「いぬ=去ぬ」=帰るの尊敬語。
「よ」は調子を整えるための呼びかけかな?
要するに、「すぐにお帰りになりますよ」だ。我々出雲弁ネイティブは、こういうほとんど別言語の言い回しを、相手次第で標準語と使い分けて話せるわけだ。
そこへいくと、静岡弁は、標準語と近すぎるぶん、使い分けが難しいのだろう。「市役所」とか、「いや」とか、どっちも静岡風にアクセントを頭に置く人がいかに多いことか。
ところで、出雲に行ってきた殿(高1女子。殿だけど女子)、本日無事ご帰還。
おかえり〜。
Posted by しぞーか式。 at
23:26
│Comments(0)
2010年08月25日
夜の散歩
今日はもらっちゃ王(6歳男子)の機嫌が悪かったので、二人で夜の散歩に出かけてみた。
夜を歩くのはなんだか特別な体験だ。まん丸の月の月明かりの下で、ゆっくり歩いたり、止まってどんな音がするのか耳をすましてみたり。虫の音、車の音、水が溝に落ちる音。
夜を一回りする間に、もらっちゃ王の機嫌はすっかり直っていた。
夜を歩くのはなんだか特別な体験だ。まん丸の月の月明かりの下で、ゆっくり歩いたり、止まってどんな音がするのか耳をすましてみたり。虫の音、車の音、水が溝に落ちる音。
夜を一回りする間に、もらっちゃ王の機嫌はすっかり直っていた。
Posted by しぞーか式。 at
22:25
│Comments(1)
2010年08月24日
売り物…
靴屋さんのディスプレイ、ではない。
ある夜に酔っ払って靴を脱いで、翌朝見たら…まるで飾ったかのような粋なおさまり具合。
別にこの靴、売り物じゃないよ。
Posted by しぞーか式。 at
23:59
│Comments(0)
2010年08月23日
いってらっしゃい
今日は殿(高1女子、殿だけど女子)が、出雲へ旅立った。新幹線と伯備線で。そして、もう着いてるはずだけど。
自分が小学生の頃、新幹線に一人乗った時のことを思い出した。かなり孤独だけど、開放感がある、あの気持ちを殿が味わってくれると嬉しい。
殿に体験して欲しいのは、誰も手伝ってくれない、でも私は行く、という悟りの気持ちだったりする。
自分が小学生の頃、新幹線に一人乗った時のことを思い出した。かなり孤独だけど、開放感がある、あの気持ちを殿が味わってくれると嬉しい。
殿に体験して欲しいのは、誰も手伝ってくれない、でも私は行く、という悟りの気持ちだったりする。
Posted by しぞーか式。 at
23:57
│Comments(0)
2010年08月22日
雨の中の涙
 映画『ブレードランナー』。何回見たか思い出せないぐらい好きな映画だ。
映画『ブレードランナー』。何回見たか思い出せないぐらい好きな映画だ。この映画の中で、レプリカント(人造人間)のルトガー ハウアーが、主人公との戦いの末に言う台詞。
「俺はお前たち人間にはとても信じられないものを見てきた。
オリオン座のそばで炎を上げた宇宙戦闘機。タンホイザー・ゲート近くの暗闇で輝いた光。
そうした瞬間もやがて消えていく。雨の中の涙のように…
そろそろ死ぬ時間だ」
読んでいて、静岡のオリオン座のことを思い出した。
最近動きを耳にしないけど、映画街はどうなるんだろう。
Posted by しぞーか式。 at
23:58
│Comments(4)
2010年08月21日
2010年08月20日
自分の輪郭
Jeffrey Deaver の"Roadside Crosses"をようやく読み終えた。読み始めてからなんと半年。でも、いったんエンジンがかかると2週間ほど。やっぱりミステリーは勢いで読まないと。
さて、ストーリーはというと、、、、
とある掲示板に投稿した人たちがつぎつぎと事件の被害者になる。犯人は、その掲示板で投稿者たちが「ネットいじめ」をした少年なのか?それとも真犯人は別にいるのか?、、、、。ネット世界で個人情報を入手して次々と犯罪を重ねる手ごわい犯人との戦いが始まった。
(ミステリーなので、ネタバレしないように一応気を使いました。)
さて、この小説のメインテーマは、「ネット社会のプライバシー」だ。人は、あまりにも安易に自分の情報の断片をネットにさらしてしまう。確かにそのパーツ一つ一つはなんでもない情報なのだが、悪意を持った誰かがそれらの情報を統合すると、その人の生活習慣や性癖の細かいところまで読み取られてしまう、ということへの警鐘なのだろう。たとえば、ブログで、「○○公園はほんとジョギングにはいいよね、俺、朝はいつもここで走ってるんだよ」と書いただけで、その○○公園で犯人に待ち伏せされる怖さ。
しかし、それとは全く次元が違うところで実はもっと怖いことがあるんだよ、ということもこの小説は明らかにしている。
たとえば、社会にとっての私とは、「男で、30代で、趣味は水泳で、静岡に暮らしていて、家族は3人で、、、」という、様々な情報の交差点(crosses)に現れてくるものだ。
ということは、私という個人にとっていくら大事な個性・属性であっても、数値化できないものは捨てられてしまうし、もっといえば、そんなものは捨て去っても「私」は特定できてしまうので、社会をまわしていくためには何の支障もない。
実は、ジェフリー・ディーバーの2009年の作品『ソウル・コレクター』(こちらは翻訳が出ている)でもサイバー犯罪が取り上げられていて、ここでも個人情報を収集・改変して無実の人を犯人に仕立て上げるという敵が登場する。しかし、この小説では、情報を悪用されることの怖さについては語っていても、個人が情報化される恐怖については語っていなかった。まさに、"Roadside Crosses"のメインテーマは、この「情報化」と「情報化から零れ落ちるもの」だとおもう。
(余談ながら、この作品、ともに犯人がつかまる後半部分がちょっとご都合主義に感じられる。かなりのラッキーと犯人の不手際であっさり解決に至ってしまうのだ。しかし、それは逆にいえば、こうした犯罪がリアルに起きたら、相当の幸運がないと解決にはいたらない、という現実の裏返しなのだろう。)
さて、例によって枕が長大になってしまったが、今日の目的は、佐藤雅彦ディレクション『これも私と認めざるをえない』展の感想をもう一度書くことだった。先日、Orangeさんからコメントをいただいて、うやむやにしかけてたこの感想を、やっぱりきちんと書いてみないとな、と思ったのだった。
7月24日に、このブログでも展覧会を見たことは書いたものの、うかつに書くと「ネタバレ」して、読んだ人が展覧会を楽しめなくなる危険を感じたので、詳細については一切触れなかったのだ。
ネタバレになったら困る、なんて、これまたミステリー小説のようだけど、、、、。
でも実際、この展覧会は、予備知識なしで会場に出かけ、作品に不意打ちをくらい、会場を出た後にグルグル回る頭を抱えて、自分がなぜあれらの作品に衝撃を感じたのかをしつこくしつこく反芻する、というふうに、つまりミステリー小説を読むように楽しむのが一番楽しめるし、それだけの気構えをもって見るにふさわしい展覧会だと思う。
展覧会のテーマは、「自分の輪郭について」(だと思う)。
「自分の輪郭」とは、他人と自己を分ける境界線のことだと言えるだろうが、一言で境界線といっても、実にいろいろな線の引き方がありえる。また、この境界線自体を、肯定的に捉える人と、否定的に捉える人といるだろう。
例えば、近年発達が目覚しい個人の認証技術も、境界線の一つと言えるだろう。認証技術の進歩によって、銀行のATMなどは大きな変化をとげた(し、これからも遂げようとしている)。
展覧会では、この技術を活用した展示も数多くあった。自分の外的特徴(指紋とか、身長とか、筆跡とか)で実にあっさりと個人が特定されるということの驚きが体験できる。指紋などよく知られた認証方法に限らず、思わぬところで(たとえば眼球の中の血管の模様で)、完璧に人間が特定できてしまう。こんなにシンプルに確実に「私」の境界線って引けちゃうんだ、技術ってすごいな、という驚きだ。
しかし、この展示に距離を置いてじっと考えてみると、本来私が持っている様々な要素は全然無視しても私が特定出来てしまうということに、じんわりと驚く。自分の人格や個性ではなく、こんな細部(例えば瞳の血管パターン)が自分を代表してしまうことがあるんだ、という、ちょっと悲しい驚きも感じる。
さて、逆に、「自分がひそかにこれが自分だと思っているもの」も、自分の輪郭と言える。
たとえば、鏡を覗くとき毎回無意識に確認している自分の顔、とか、自分の幼少の記憶とか。これは上記の数値化できる個人認証とは全く別に、無意識ながら日々の暮らしの中では、自分の輪郭を保障する大事な要素だ。
さて、ネタバレの危険があるのでここから話はグンと抽象的にならざるを得ないのだけれど、展覧会では、こうした指標の一つ一つを作品と言う形で明確に提示してくれる。展示を見た私たちは、今まで無意識に指標にしていた一つ一つの検証を迫られる。
そうした指標で私がどれだけ他人と区別可能なのか。また、その指標は私たちが思っているほど確実でゆるぎないものなのか。
こうした遊びめいた思考実験の果てに、とても自分と認められないような何かが、展示を身終えると自分と感じられるようになる。逆に、明らかに自分の一部と思っていた何かへの疑いが生まれてくる。
実際、とある展示(ヒントは「金魚」)を見ているとき、私は、足元がふわーっとして、弱い吐き気を感じるほどショックだった。自分の輪郭が溶け出すような感覚を味わったからだと思う。
これは、かなりに哲学的な問題だ。自己と他者。
しかし、そうした日常の自明性への疑いを、あくまでもエンターテイメントとして提示してくれるこの展覧会の凄みがある。

先日、自分の指をきっちり認証してくれなかった銀行のATMと出会って足元がぐらぐらする感じを味わった、あのエピソードをまた思い出してしまった。あれも、「自分の輪郭が溶け出す」体験の一つだった。
うーん、かなりに舌足らずではあるが、今現在はこれぐらいが自分の限界かも。
もっとうまく整理できれば、いつかきっと。
「これも自分と認めざるをえない」展
東京ミッドタウン ガーデン内 「21-21 design sight」
港区赤坂9-7-6
11月3日まで
さて、ストーリーはというと、、、、
とある掲示板に投稿した人たちがつぎつぎと事件の被害者になる。犯人は、その掲示板で投稿者たちが「ネットいじめ」をした少年なのか?それとも真犯人は別にいるのか?、、、、。ネット世界で個人情報を入手して次々と犯罪を重ねる手ごわい犯人との戦いが始まった。
(ミステリーなので、ネタバレしないように一応気を使いました。)
さて、この小説のメインテーマは、「ネット社会のプライバシー」だ。人は、あまりにも安易に自分の情報の断片をネットにさらしてしまう。確かにそのパーツ一つ一つはなんでもない情報なのだが、悪意を持った誰かがそれらの情報を統合すると、その人の生活習慣や性癖の細かいところまで読み取られてしまう、ということへの警鐘なのだろう。たとえば、ブログで、「○○公園はほんとジョギングにはいいよね、俺、朝はいつもここで走ってるんだよ」と書いただけで、その○○公園で犯人に待ち伏せされる怖さ。
しかし、それとは全く次元が違うところで実はもっと怖いことがあるんだよ、ということもこの小説は明らかにしている。
たとえば、社会にとっての私とは、「男で、30代で、趣味は水泳で、静岡に暮らしていて、家族は3人で、、、」という、様々な情報の交差点(crosses)に現れてくるものだ。
ということは、私という個人にとっていくら大事な個性・属性であっても、数値化できないものは捨てられてしまうし、もっといえば、そんなものは捨て去っても「私」は特定できてしまうので、社会をまわしていくためには何の支障もない。
実は、ジェフリー・ディーバーの2009年の作品『ソウル・コレクター』(こちらは翻訳が出ている)でもサイバー犯罪が取り上げられていて、ここでも個人情報を収集・改変して無実の人を犯人に仕立て上げるという敵が登場する。しかし、この小説では、情報を悪用されることの怖さについては語っていても、個人が情報化される恐怖については語っていなかった。まさに、"Roadside Crosses"のメインテーマは、この「情報化」と「情報化から零れ落ちるもの」だとおもう。
(余談ながら、この作品、ともに犯人がつかまる後半部分がちょっとご都合主義に感じられる。かなりのラッキーと犯人の不手際であっさり解決に至ってしまうのだ。しかし、それは逆にいえば、こうした犯罪がリアルに起きたら、相当の幸運がないと解決にはいたらない、という現実の裏返しなのだろう。)
さて、例によって枕が長大になってしまったが、今日の目的は、佐藤雅彦ディレクション『これも私と認めざるをえない』展の感想をもう一度書くことだった。先日、Orangeさんからコメントをいただいて、うやむやにしかけてたこの感想を、やっぱりきちんと書いてみないとな、と思ったのだった。
7月24日に、このブログでも展覧会を見たことは書いたものの、うかつに書くと「ネタバレ」して、読んだ人が展覧会を楽しめなくなる危険を感じたので、詳細については一切触れなかったのだ。
ネタバレになったら困る、なんて、これまたミステリー小説のようだけど、、、、。
でも実際、この展覧会は、予備知識なしで会場に出かけ、作品に不意打ちをくらい、会場を出た後にグルグル回る頭を抱えて、自分がなぜあれらの作品に衝撃を感じたのかをしつこくしつこく反芻する、というふうに、つまりミステリー小説を読むように楽しむのが一番楽しめるし、それだけの気構えをもって見るにふさわしい展覧会だと思う。
展覧会のテーマは、「自分の輪郭について」(だと思う)。
「自分の輪郭」とは、他人と自己を分ける境界線のことだと言えるだろうが、一言で境界線といっても、実にいろいろな線の引き方がありえる。また、この境界線自体を、肯定的に捉える人と、否定的に捉える人といるだろう。
例えば、近年発達が目覚しい個人の認証技術も、境界線の一つと言えるだろう。認証技術の進歩によって、銀行のATMなどは大きな変化をとげた(し、これからも遂げようとしている)。
展覧会では、この技術を活用した展示も数多くあった。自分の外的特徴(指紋とか、身長とか、筆跡とか)で実にあっさりと個人が特定されるということの驚きが体験できる。指紋などよく知られた認証方法に限らず、思わぬところで(たとえば眼球の中の血管の模様で)、完璧に人間が特定できてしまう。こんなにシンプルに確実に「私」の境界線って引けちゃうんだ、技術ってすごいな、という驚きだ。
しかし、この展示に距離を置いてじっと考えてみると、本来私が持っている様々な要素は全然無視しても私が特定出来てしまうということに、じんわりと驚く。自分の人格や個性ではなく、こんな細部(例えば瞳の血管パターン)が自分を代表してしまうことがあるんだ、という、ちょっと悲しい驚きも感じる。
さて、逆に、「自分がひそかにこれが自分だと思っているもの」も、自分の輪郭と言える。
たとえば、鏡を覗くとき毎回無意識に確認している自分の顔、とか、自分の幼少の記憶とか。これは上記の数値化できる個人認証とは全く別に、無意識ながら日々の暮らしの中では、自分の輪郭を保障する大事な要素だ。
さて、ネタバレの危険があるのでここから話はグンと抽象的にならざるを得ないのだけれど、展覧会では、こうした指標の一つ一つを作品と言う形で明確に提示してくれる。展示を見た私たちは、今まで無意識に指標にしていた一つ一つの検証を迫られる。
そうした指標で私がどれだけ他人と区別可能なのか。また、その指標は私たちが思っているほど確実でゆるぎないものなのか。
こうした遊びめいた思考実験の果てに、とても自分と認められないような何かが、展示を身終えると自分と感じられるようになる。逆に、明らかに自分の一部と思っていた何かへの疑いが生まれてくる。
実際、とある展示(ヒントは「金魚」)を見ているとき、私は、足元がふわーっとして、弱い吐き気を感じるほどショックだった。自分の輪郭が溶け出すような感覚を味わったからだと思う。
これは、かなりに哲学的な問題だ。自己と他者。
しかし、そうした日常の自明性への疑いを、あくまでもエンターテイメントとして提示してくれるこの展覧会の凄みがある。

先日、自分の指をきっちり認証してくれなかった銀行のATMと出会って足元がぐらぐらする感じを味わった、あのエピソードをまた思い出してしまった。あれも、「自分の輪郭が溶け出す」体験の一つだった。
うーん、かなりに舌足らずではあるが、今現在はこれぐらいが自分の限界かも。
もっとうまく整理できれば、いつかきっと。
「これも自分と認めざるをえない」展
東京ミッドタウン ガーデン内 「21-21 design sight」
港区赤坂9-7-6
11月3日まで
2010年08月19日
暑さでボー
 「タバコって何歳から吸っていいの?」と、姫(小4女子)。
「タバコって何歳から吸っていいの?」と、姫(小4女子)。父「二十歳からだよ。」
もらっちゃ王(6歳男子)「ふーん。お父さんって何歳?」
父「◯十◯歳。」
も「ああ、だからお父さんはとっくの昔に吸いおわってんだね!」
(うちは誰も吸わないので。)
なんて会話をしつつ、今日も猛暑。日々暑くて、ついになつかしの天花粉を取り出した。
天花粉って、名前の響きもいいし、何よりサラサラになるので湿度が高い時はとても快適になる。
今日の風呂上がりのもらっちゃ王、上から下まで真っ白にしてやった。
2010年08月18日
夏限定


清水まで映画を見に行った帰り道。汗をだらだら流しつつ、姫(小4女子)と生ジュース。
この日は晩夏の数日間のみ限定というプラムジュース!酸っぱくて甘くて、キリリ。
タケダフルーツ
静岡市清水区銀座1−9 清水中央銀座(清水銀座と駅前銀座の間)
054(364)3050
9:30〜19:00 水休
Posted by しぞーか式。 at
22:15
│Comments(2)
2010年08月17日
闇にふわふわ
美保の水族館の夜間開館に行ってきた。
学芸員さんの解説付きで、夜の魚たちと出会えるという企画。百匹ほどが塊になってうごめくクマノミ(海ならイソギンチャクに
隠れて休む習性が、水槽の
中だと互いに魚塊を作らせるらしい)とか、光る魚色々など、充実した展示だった…が、私はクラゲにココロ奪われてしまい、かなりの時間をクラゲの前で過ごしてしまった。
欲を言えば、ふわふわ漂うクラゲの前にふかふかのソファを置いて欲しいと思った。
Posted by しぞーか式。 at
23:05
│Comments(2)
2010年08月16日
2010年08月15日
2010年08月14日
怪談としての『1Q84』
もう一月以上もまえになるけど、「考える人」という雑誌に村上春樹のロングインタビューが掲載されていた。
書店では「『1Q84』を読みおえてからお読みください」というふうに広告されていたとおり、話題作『1Q84』のネタバレありの長い長いインタビュー。さらに、これまでの村上作品を振り返る裏話が多数展開されていて、読みどころ満載だった。
なかでも、村上さんが、自分の作品を、世界の古典や現代文学のなかでどんな位置にいるべきなのかをかなり意識的に書いていることがわかるところは、とても興味深く読んだ。
さて、このインタビューの中には、村上春樹の
あのですね、『1Q84』は、簡単に言ってしまえば因縁話なんです。圓朝の『真景累ヶ淵』に似ているところがあります。僕のすごく好きな物語なんだけど。
という発言があって、面白そうだったので岩波文庫で探して読み始めた。先月「ひえひえ」というポストを書いたのはこういう次第だった。
さて、この『累ガ淵』は、落語家、、、、というよりむしろ『牡丹灯篭』などの怪談話で有名な三遊亭圓朝が、当時流布した怪談話をもとにした創作怪談。親が犯してしまった残酷な罪の報いが、子供、孫の代まで続いて祟りつづけるという長い長いお話だ。
口述筆記の形をとっているので、物語の構造にもかなり特徴がある。
落語でいう枕のような導入部があり、本の要所要所で何度か中締めがある。そして、また枕とあらすじがあって話が再開する。そのつど、「現代では幽霊なんていないことになっている」「でも、いると思う人にはいるんです」という、メタレベルの怪談解釈が織り込まれたりするのが面白い。
さて、そういう構造にひっぱられてか、物語の前半には要所要所で登場した亡霊が、物語の中盤から登場しなくなるのがとても興味深かった。たとえば、物語の前半では、悪役の男が、妻の顔が亡霊に見えて思わず妻を切り殺すシーンがある。つまり、登場人物は十分に罪の自覚を持っていて、それゆえに気に病み、幽霊を見てしまう、と読める。
つまり、この前半に登場する亡霊は、近代的な科学の視点からも「気のせい」という解釈が可能な存在なのだ。そもそも、題名の真景は神経から来ているらしいし。
ところが、物語後半になると、登場人物は、途中まで自分が祟られているということすら気づかず、運命に翻弄されるというような物語になっていく。そして、自分が祟られていたことは、悲劇が一通り起こってしまってから後付けで説明される。つまり、「運命」「宿命」というものの怖さが前面に出てくるのだ。
もちろん、物語の後半になっても要所要所では「美しい女の顔の傷」など、物語前半の亡霊を思い出させる描写は出てくるのだけれど、怖さの質が前半と後半で全く違っているのは明らかだ。
これは、祟りというものが、世代が下っていくにつれ幽霊個人(?)を離れて血筋の問題へと抽象化されていく過程のようにも見える。
物語前半で展開される、自分の悪行の報いとしての祟りへの恐怖。一方、物語後半では、登場人物は先祖の悪行を知らないのにひどい運命に翻弄される恐怖。
彼らも悪人ではあるけれど、ひどい目にあう理由はその悪行の報いではなく、先祖の悪行の祟り。たしかに子孫たちもひどい行いはするけれど、その悪行さえ、先祖の代からの祟りかもしれないのだ。
怪談話としての評価は前半の方が高く、こちらしか演じられないことも多いそうだが、私にとっては、この後半部分のほうが、不条理で怖い。なんだか、ギリシャ悲劇のような。
大きく話は跳ぶけど、先日見たアラン・パーカーの映画『エンゼル・ハート』も、本人のあずかり知らないところであらかじめ運命が決められている恐怖を描いた映画だったな。あれも怖かった。
自分は何も悪いことをしていないのに、悪い運命に見舞われたとき、そこに「先祖の悪行」という、自分ではどうしようもないことを後付けで理由に挙げられると、人はどこか安心できるのだろうか。それとも、絶望的な恐怖を感じるのだろうか。
ともかく、『1Q84』も、そうした物語の伝統をふまえていると思えば、なんだかまた広がりを持って読める気がする。
さてと、実はここまでは長い長い前ふりでして、、、、。
平野雅彦さんの「脳内探訪」を読んだかたならご存知だろうが、4夜連続の怪談話が昨日から始まっている。そして、今夜はまさにその円朝ゆかりの「累(かさね)」のお話、、、、、行きたいのだがどうしても所要があっていけない。
こちらが日程などの詳細。
幸運にも行けた方は、ぜひ感想を聞かせてください。
書店では「『1Q84』を読みおえてからお読みください」というふうに広告されていたとおり、話題作『1Q84』のネタバレありの長い長いインタビュー。さらに、これまでの村上作品を振り返る裏話が多数展開されていて、読みどころ満載だった。
なかでも、村上さんが、自分の作品を、世界の古典や現代文学のなかでどんな位置にいるべきなのかをかなり意識的に書いていることがわかるところは、とても興味深く読んだ。
さて、このインタビューの中には、村上春樹の
あのですね、『1Q84』は、簡単に言ってしまえば因縁話なんです。圓朝の『真景累ヶ淵』に似ているところがあります。僕のすごく好きな物語なんだけど。
という発言があって、面白そうだったので岩波文庫で探して読み始めた。先月「ひえひえ」というポストを書いたのはこういう次第だった。
さて、この『累ガ淵』は、落語家、、、、というよりむしろ『牡丹灯篭』などの怪談話で有名な三遊亭圓朝が、当時流布した怪談話をもとにした創作怪談。親が犯してしまった残酷な罪の報いが、子供、孫の代まで続いて祟りつづけるという長い長いお話だ。
口述筆記の形をとっているので、物語の構造にもかなり特徴がある。
落語でいう枕のような導入部があり、本の要所要所で何度か中締めがある。そして、また枕とあらすじがあって話が再開する。そのつど、「現代では幽霊なんていないことになっている」「でも、いると思う人にはいるんです」という、メタレベルの怪談解釈が織り込まれたりするのが面白い。
さて、そういう構造にひっぱられてか、物語の前半には要所要所で登場した亡霊が、物語の中盤から登場しなくなるのがとても興味深かった。たとえば、物語の前半では、悪役の男が、妻の顔が亡霊に見えて思わず妻を切り殺すシーンがある。つまり、登場人物は十分に罪の自覚を持っていて、それゆえに気に病み、幽霊を見てしまう、と読める。
つまり、この前半に登場する亡霊は、近代的な科学の視点からも「気のせい」という解釈が可能な存在なのだ。そもそも、題名の真景は神経から来ているらしいし。
ところが、物語後半になると、登場人物は、途中まで自分が祟られているということすら気づかず、運命に翻弄されるというような物語になっていく。そして、自分が祟られていたことは、悲劇が一通り起こってしまってから後付けで説明される。つまり、「運命」「宿命」というものの怖さが前面に出てくるのだ。
もちろん、物語の後半になっても要所要所では「美しい女の顔の傷」など、物語前半の亡霊を思い出させる描写は出てくるのだけれど、怖さの質が前半と後半で全く違っているのは明らかだ。
これは、祟りというものが、世代が下っていくにつれ幽霊個人(?)を離れて血筋の問題へと抽象化されていく過程のようにも見える。
物語前半で展開される、自分の悪行の報いとしての祟りへの恐怖。一方、物語後半では、登場人物は先祖の悪行を知らないのにひどい運命に翻弄される恐怖。
彼らも悪人ではあるけれど、ひどい目にあう理由はその悪行の報いではなく、先祖の悪行の祟り。たしかに子孫たちもひどい行いはするけれど、その悪行さえ、先祖の代からの祟りかもしれないのだ。
怪談話としての評価は前半の方が高く、こちらしか演じられないことも多いそうだが、私にとっては、この後半部分のほうが、不条理で怖い。なんだか、ギリシャ悲劇のような。
大きく話は跳ぶけど、先日見たアラン・パーカーの映画『エンゼル・ハート』も、本人のあずかり知らないところであらかじめ運命が決められている恐怖を描いた映画だったな。あれも怖かった。
自分は何も悪いことをしていないのに、悪い運命に見舞われたとき、そこに「先祖の悪行」という、自分ではどうしようもないことを後付けで理由に挙げられると、人はどこか安心できるのだろうか。それとも、絶望的な恐怖を感じるのだろうか。
ともかく、『1Q84』も、そうした物語の伝統をふまえていると思えば、なんだかまた広がりを持って読める気がする。
さてと、実はここまでは長い長い前ふりでして、、、、。
平野雅彦さんの「脳内探訪」を読んだかたならご存知だろうが、4夜連続の怪談話が昨日から始まっている。そして、今夜はまさにその円朝ゆかりの「累(かさね)」のお話、、、、、行きたいのだがどうしても所要があっていけない。
こちらが日程などの詳細。
幸運にも行けた方は、ぜひ感想を聞かせてください。
2010年08月13日
お暑いのがお好き
 なわけはないんだけど、呉服町の夜店市で、ガバオ飯(だっけ?)でご機嫌。からーい具に、香りのいいタイ米が合う。
なわけはないんだけど、呉服町の夜店市で、ガバオ飯(だっけ?)でご機嫌。からーい具に、香りのいいタイ米が合う。表示を見てみたら、やっぱりアローイアロイの出店だった。500円なり。
Posted by しぞーか式。 at
23:58
│Comments(1)
2010年08月12日
夏休みの子供(2)
おととい書いた、静岡市立美術館での矢野顕子さんのコンサートレビュー。
頭の中でいろいろ転がしていくうちに、矢野顕子さんとの出会いをいろいろ思い出してきたので、備忘録的に書いておく。
私が矢野顕子というアーティストを知ったのは小学生のころ。当時、初めて一人の部屋をもらって、自分のペースで寝起きすることになったのだった。そのとき、枕元にあったのが時計つきラジオで、夜、寝る前にいろいろとチャンネルをさぐるうち、NHKのAMで放送していた「若いこだま」という番組と出会うことになった。
ここで、なんだかふわふわとした、何を言っているのかちゃんとはわからない、でもきっと自分の言葉で自分の思いを語っている不思議なしゃべり方をする女の人と出会ったのだった。
もしかしたら、音楽と同じぐらい、そのしゃべり方にも惹かれたということを、今思い出した。
この番組は、AMのくせにかなり先進的な音楽を流していた。いや、AMのくせにというのはフェアじゃないな。クラシックやジャズが強かったFMで紹介しきれない若い日本の音楽家が活躍できる唯一の場所だったのだ。
今、当時の文献を見直すと、矢野さんの番組には、ゲストには細野晴臣さんや本田美奈子さんなどそうそうたるメンバーがゲストとして登場していたし、矢野さん以外の曜日には、甲斐バンドの甲斐よしひろさんや、荒井由美さん(結婚前のユーミン!)などがDJを勤めていたらしい。
らしい、というのは、ひとつには矢野顕子があまり強烈過ぎてほかのDJのことを覚えていないということだ。
そういえば、そのラジオの音量を上げて、近くでカセットレコーダーを回して録音し(ラインじゃないから当然ひどい音質だ)、母に矢野顕子のトークや、変拍子の「丘を越えて」を聞かせたことがある。
母の感想は、「なにこの人、おかしいんじゃない」。・・・当時の大人としては正常な反応なのだけど、矢野さんを通して音楽に初めてであった小学生にしてみれば、「自分が魅力的だと思った、この音楽は普通じゃないんだ」と思い知らされた。そして、思い知りつつもこれが自分の音楽を聴くときのスタンダードになってしまって今に至るという、、、、、。
でも、そういう雷に打たれるような体験があるからこそ、今もこんなに音楽を聴くのが楽しいと思えば、矢野顕子も、そしてそれを「おかしいんじゃない」と言ってくれた母も、どっちもありがたい気がする。
頭の中でいろいろ転がしていくうちに、矢野顕子さんとの出会いをいろいろ思い出してきたので、備忘録的に書いておく。
私が矢野顕子というアーティストを知ったのは小学生のころ。当時、初めて一人の部屋をもらって、自分のペースで寝起きすることになったのだった。そのとき、枕元にあったのが時計つきラジオで、夜、寝る前にいろいろとチャンネルをさぐるうち、NHKのAMで放送していた「若いこだま」という番組と出会うことになった。
ここで、なんだかふわふわとした、何を言っているのかちゃんとはわからない、でもきっと自分の言葉で自分の思いを語っている不思議なしゃべり方をする女の人と出会ったのだった。
もしかしたら、音楽と同じぐらい、そのしゃべり方にも惹かれたということを、今思い出した。
この番組は、AMのくせにかなり先進的な音楽を流していた。いや、AMのくせにというのはフェアじゃないな。クラシックやジャズが強かったFMで紹介しきれない若い日本の音楽家が活躍できる唯一の場所だったのだ。
今、当時の文献を見直すと、矢野さんの番組には、ゲストには細野晴臣さんや本田美奈子さんなどそうそうたるメンバーがゲストとして登場していたし、矢野さん以外の曜日には、甲斐バンドの甲斐よしひろさんや、荒井由美さん(結婚前のユーミン!)などがDJを勤めていたらしい。
らしい、というのは、ひとつには矢野顕子があまり強烈過ぎてほかのDJのことを覚えていないということだ。
そういえば、そのラジオの音量を上げて、近くでカセットレコーダーを回して録音し(ラインじゃないから当然ひどい音質だ)、母に矢野顕子のトークや、変拍子の「丘を越えて」を聞かせたことがある。
母の感想は、「なにこの人、おかしいんじゃない」。・・・当時の大人としては正常な反応なのだけど、矢野さんを通して音楽に初めてであった小学生にしてみれば、「自分が魅力的だと思った、この音楽は普通じゃないんだ」と思い知らされた。そして、思い知りつつもこれが自分の音楽を聴くときのスタンダードになってしまって今に至るという、、、、、。
でも、そういう雷に打たれるような体験があるからこそ、今もこんなに音楽を聴くのが楽しいと思えば、矢野顕子も、そしてそれを「おかしいんじゃない」と言ってくれた母も、どっちもありがたい気がする。



 若干の想像力なしには、点が点在しているだけ、という道路を見かけた。
若干の想像力なしには、点が点在しているだけ、という道路を見かけた。